この世界にふたりだけ2
- Digital500 JPY

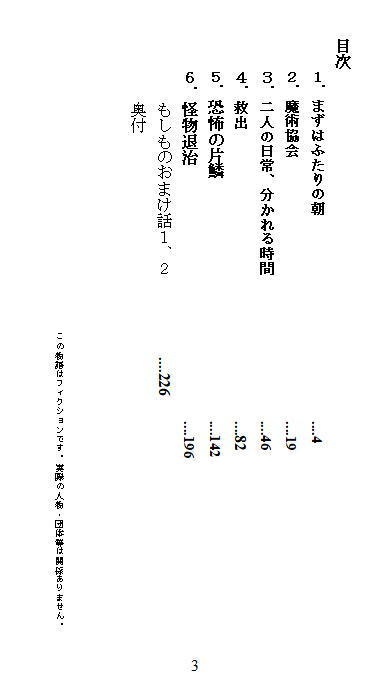
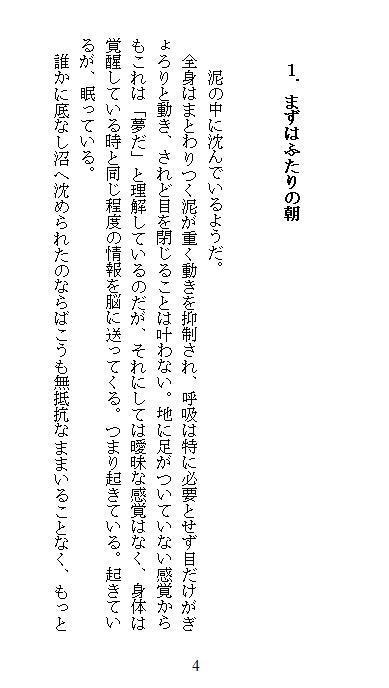
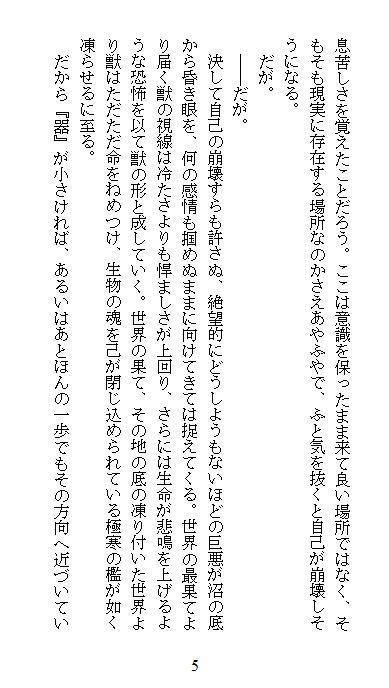
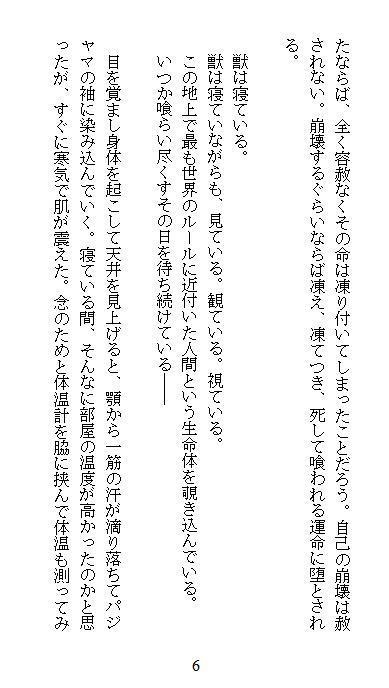
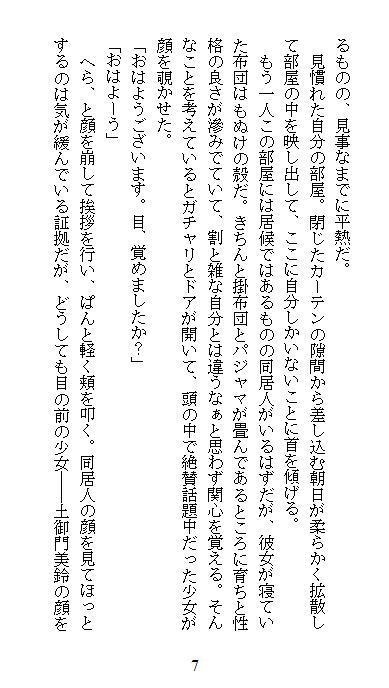
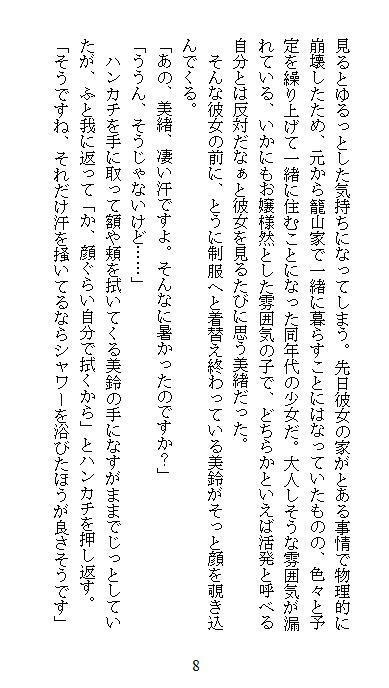
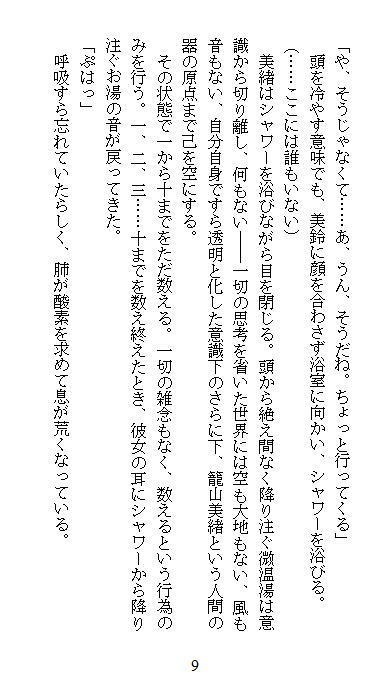
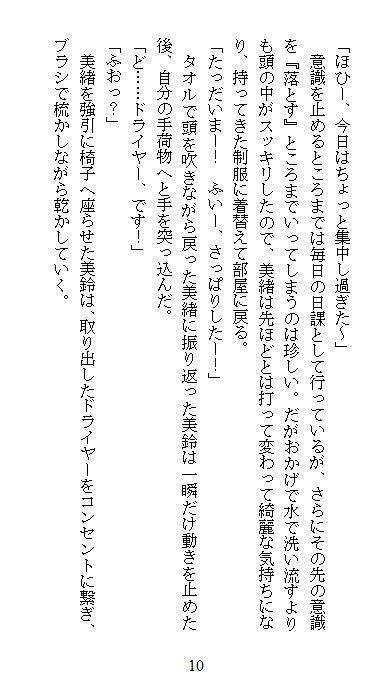
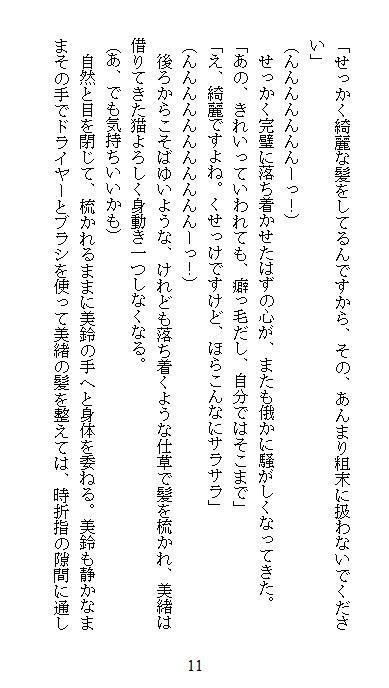
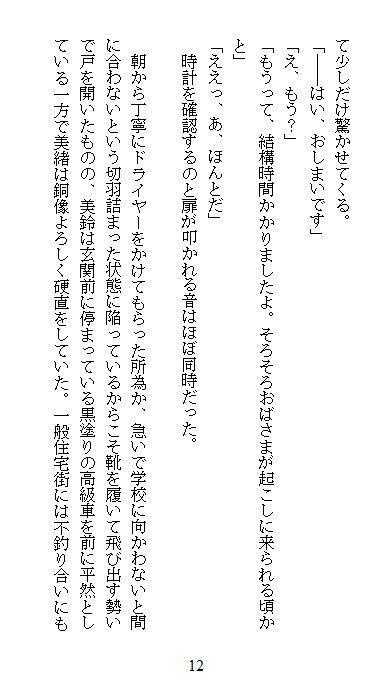
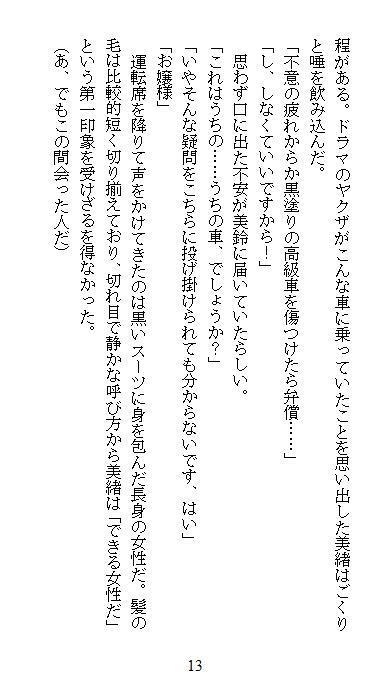
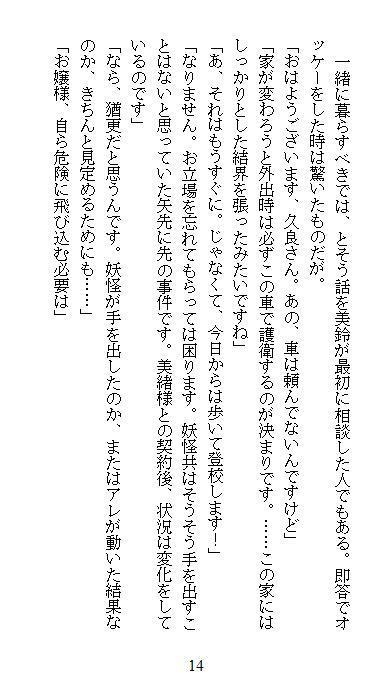
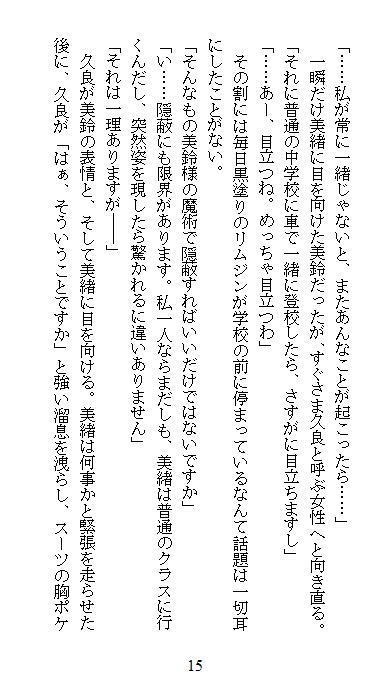
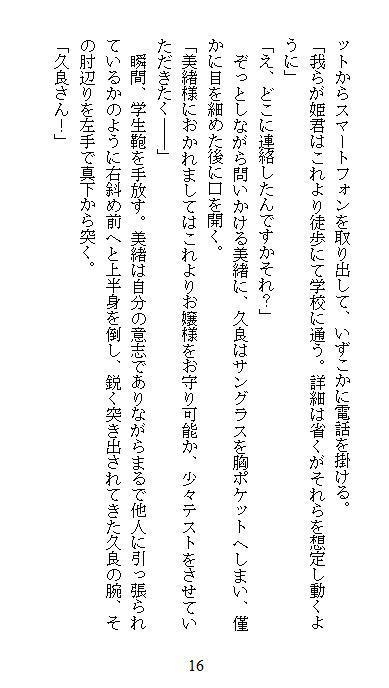
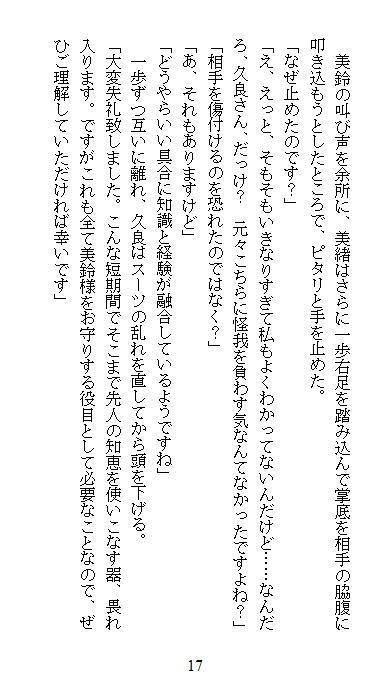
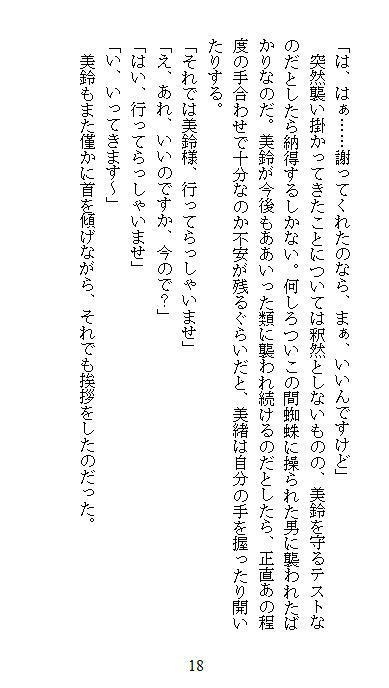
著者:平乃ひら 表紙:みちょこ ロゴ・キャラクターデザイン:みちょこ ページ数:237(表紙・裏表紙抜かす) 「ちゃんとわかってる。美鈴を守るって決めたんだよ、私は」 気付けば一つ屋根の下。中学生で夫婦となった美緒と美鈴は一緒に暮らすことになって間もない頃、まだどことなくぎこちないふたりに容赦なく襲いかかるドキドキ試練……と思いきや、美鈴を守る美緒が攫われて事態は急転していくことになり、さらに美緒が連れ去られた場所にはトンデモナイモノがいた……! ――これは分離された小さくも余りに巨大な黒い獣が。 試しに人類の歴史と力を喰らおうとする恐怖に立ち向かう話―― 中学生百合夫婦伝奇ストーリー、第二幕――!
1.まずはふたりの朝
泥の中に沈んでいるようだ。 全身はまとわりつく泥が重く動きを抑制され、呼吸は特に必要とせず目だけがぎょろりと動き、されど目を閉じることは叶わない。地に足がついていない感覚からもこれは「夢だ」と理解しているのだが、それにしては曖昧な感覚はなく、身体は覚醒している時と同じ程度の情報を脳に送ってくる。つまり起きている。起きているが、眠っている。 誰かに底なし沼へ沈められたのならばこうも無抵抗なままいることなく、もっと息苦しさを覚えたことだろう。ここは意識を保ったまま来て良い場所ではなく、そもそも現実に存在する場所なのかさえあやふやで、ふと気を抜くと自己が崩壊しそうになる。 だが。 ――だが。 決して自己の崩壊すらも許さぬ、絶望的にどうしようもないほどの巨悪が沼の底から昏き眼を、何の感情も掴めぬままに向けてきては捉えてくる。世界の最果てより届く獣の視線は冷たさよりも悍ましさが上回り、さらには生命が悲鳴を上げるような恐怖を以て獣の形と成していく。世界の果て、その地の底の凍り付いた世界より獣はただただ命をねめつけ、生物の魂を己が閉じ込められている極寒の檻が如く凍らせるに至る。 だから『器』が小さければ、あるいはあとほんの一歩でもその方向へ近づいていたならば、全く容赦なくその命は凍り付いてしまったことだろう。自己の崩壊は赦されない。崩壊するぐらいならば凍え、凍てつき、死して喰われる運命に堕とされる。 獣は寝ている。 獣は寝ていながらも、見ている。観ている。視ている。 この地上で最も世界のルールに近付いた人間という生命体を覗き込んでいる。 いつか喰らい尽くすその日を待ち続けている―― 目を覚まし身体を起こして天井を見上げると、顎から一筋の汗が滴り落ちてパジャマの袖に染み込んでいく。寝ている間、そんなに部屋の温度が高かったのかと思ったが、すぐに寒気で肌が震えた。念のためと体温計を脇に挟んで体温も測ってみるものの、見事なまでに平熱だ。 見慣れた自分の部屋。閉じたカーテンの隙間から差し込む朝日が柔らかく拡散して部屋の中を映し出して、ここに自分しかいないことに首を傾げる。 もう一人この部屋には居候ではあるものの同居人がいるはずだが、彼女が寝ていた布団はもぬけの殻だ。きちんと掛布団とパジャマが畳んであるところに育ちと性格の良さが滲みでていて、割と雑な自分とは違うなぁと思わず関心を覚える。そんなことを考えているとガチャリとドアが開いて、頭の中で絶賛話題中だった少女が顔を覗かせた。 「おはようございます。目、覚めましたか?」 「おはよーう」 へら、と顔を崩して挨拶を行い、ぱんと軽く頬を叩く。同居人の顔を見てほっとするのは気が緩んでいる証拠だが、どうしても目の前の少女――土御門美鈴の顔を見るとゆるっとした気持ちになってしまう。先日彼女の家がとある事情で物理的に崩壊したため、元から籠山家で一緒に暮らすことにはなっていたものの、色々と予定を繰り上げて一緒に住むことになった同年代の少女だ。大人しそうな雰囲気が漏れている、いかにもお嬢様然とした雰囲気の子で、どちらかといえば活発と呼べる自分とは反対だなぁと彼女を見るたびに思う美緒だった。 そんな彼女の前に、とうに制服へと着替え終わっている美鈴がそっと顔を覗き込んでくる。 「あの、美緒、凄い汗ですよ。そんなに暑かったのですか?」 「ううん、そうじゃないけど……」 ハンカチを手に取って額や頬を拭いてくる美鈴の手になすがままでじっとしていたが、ふと我に返って「か、顔ぐらい自分で拭くから」とハンカチを押し返す。 「そうですね、それだけ汗を掻いてるならシャワーを浴びたほうが良さそうです」 「や、そうじゃなくて……あ、うん、そうだね。ちょっと行ってくる」 頭を冷やす意味でも、美鈴に顔を合わさず浴室に向かい、シャワーを浴びる。 (……ここには誰もいない) 美緒はシャワーを浴びながら目を閉じる。頭から絶え間なく降り注ぐ微温湯は意識から切り離し、何もない――一切の思考を省いた世界には空も大地もない、風も音もない、自分自身ですら透明と化した意識下のさらに下、籠山美緒という人間の器の原点まで己を空にする。 その状態で一から十までをただ数える。一切の雑念もなく、数えるという行為のみを行う。一、二、三……十までを数え終えたとき、彼女の耳にシャワーから降り注ぐお湯の音が戻ってきた。 「ぷはっ」 呼吸すら忘れていたらしく、肺が酸素を求めて息が荒くなっている。 「ほひー、今日はちょっと集中し過ぎた~」 意識を止めるところまでは毎日の日課として行っているが、さらにその先の意識を『落とす』ところまでいってしまうのは珍しい。だがおかげで水で洗い流すよりも頭の中がスッキリしたので、美緒は先ほどとは打って変わって綺麗な気持ちになり、持ってきた制服に着替えて部屋に戻る。 「たっだいまー! ふいー、さっぱりしたー!」 タオルで頭を吹きながら戻った美緒に振り返った美鈴は一瞬だけ動きを止めた後、自分の手荷物へと手を突っ込んだ。 「ど……ドライヤー、です!」 「ふおっ?」 美緒を強引に椅子へ座らせた美鈴は、取り出したドライヤーをコンセントに繋ぎ、ブラシで梳かしながら乾かしていく。 「せっかく綺麗な髪をしてるんですから、その、あんまり粗末に扱わないでください」 (んんんんんんんーっ!) せっかく完璧に落ち着かせたはずの心が、またも俄かに騒がしくなってきた。 「あの、きれいっていわれても、癖っ毛だし、自分ではそこまで」 「え、綺麗ですよね。くせっけですけど、ほらこんなにサラサラ」 (んんんんんんんんんんんーっ!) 後ろからこそばゆいような、けれども落ち着くような仕草で髪を梳かれ、美緒は借りてきた猫よろしく身動き一つしなくなる。 (あ、でも気持ちいいかも) 自然と目を閉じて、梳かれるままに美鈴の手へと身体を委ねる。美鈴も静かなままその手でドライヤーとブラシを使って美緒の髪を整えては、時折指の隙間に通して少しだけ驚かせてくる。 「――はい、おしまいです」 「え、もう?」 「もうって、結構時間かかりましたよ。そろそろおばさまが起こしに来られる頃かと」 「ええっ、あ、ほんとだ」 時計を確認するのと扉が叩かれる音はほぼ同時だった。 朝から丁寧にドライヤーをかけてもらった所為か、急いで学校に向かわないと間に合わないという切羽詰まった状態に陥っているからこそ靴を履いて飛び出す勢いで戸を開いたものの、美鈴は玄関前に停まっている黒塗りの高級車を前に平然としている一方で美緒は銅像よろしく硬直をしていた。一般住宅街には不釣り合いにも程がある。ドラマのヤクザがこんな車に乗っていたことを思い出した美緒はごくりと唾を飲み込んだ。 「不意の疲れからか黒塗りの高級車を傷つけたら弁償……」 「し、しなくていいですから!」 思わず口に出た不安が美鈴に届いていたらしい。 「これはうちの……うちの車、でしょうか?」 「いやそんな疑問をこちらに投げ掛けられても分からないです、はい」 「お嬢様」 運転席を降りて声をかけてきたのは黒いスーツに身を包んだ長身の女性だ。髪の毛は比較的短く切り揃えており、切れ目で静かな呼び方から美緒は「できる女性だ」という第一印象を受けざるを得なかった。 (あ、でもこの間会った人だ) 一緒に暮らすべきでは、とそう話を美鈴が最初に相談した人でもある。即答でオッケーをした時は驚いたものだが。 「おはようございます、久良さん。あの、車は頼んでないんですけど」 「家が変わろうと外出時は必ずこの車で護衛するのが決まりです。……この家にはしっかりとした結界を張ったみたいですね」 「あ、それはもうすぐに。じゃなくて、今日からは歩いて登校します!」 「なりません。お立場を忘れてもらっては困ります。妖怪共はそうそう手を出すことはないと思っていた矢先に先の事件です。美緒様との契約後、状況は変化をしているのです」 「なら、猶更だと思うんです。妖怪が手を出したのか、またはアレが動いた結果なのか、きちんと見定めるためにも……」 「お嬢様、自ら危険に飛び込む必要は」 「……私が常に一緒じゃないと、またあんなことが起こったら……」 一瞬だけ美緒に目を向けた美鈴だったが、すぐさま久良と呼ぶ女性へと向き直る。 「それに普通の中学校に車で一緒に登校したら、さすがに目立ちますし」 「……あー、目立つね。めっちゃ目立つわ」 その割には毎日黒塗りのリムジンが学校の前に停まっているなんて話題は一切耳にしたことがない。 「そんなもの美鈴様の魔術で隠蔽すればいいだけではないですか」 「い……隠蔽にも限界があります。私一人ならまだしも、美緒は普通のクラスに行くんだし、突然姿を現したら驚かれるに違いありません」 「それは一理ありますが――」 久良が美鈴の表情と、そして美緒に目を向ける。美緒は何事かと緊張を走らせた後に、久良が「はぁ、そういうことですか」と強い溜息を洩らし、スーツの胸ポケットからスマートフォンを取り出して、いずこかに電話を掛ける。 「我らが姫君はこれより徒歩にて学校に通う。詳細は省くがそれらを想定し動くように」 「え、どこに連絡したんですかそれ?」 ぞっとしながら問いかける美緒に、久良はサングラスを胸ポケットへしまい、僅かに目を細めた後に口を開く。 「美緒様におかれましてはこれよりお嬢様をお守り可能か、少々テストをさせていただきたく――」 瞬間、学生鞄を手放す。美緒は自分の意志でありながらまるで他人に引っ張られているかのように右斜め前へと上半身を倒し、鋭く突き出されてきた久良の腕、その肘辺りを左手で真下から突く。 「久良さん!」 美鈴の叫び声を余所に、美緒はさらに一歩右足を踏み込んで掌底を相手の脇腹に叩き込もうとしたところで、ピタリと手を止めた。 「なぜ止めたのです?」 「え、えっと、そもそもいきなりすぎて私もよくわかってないんだけど……なんだろ、久良さん、だっけ? 元々こちらに怪我を負わす気なんてなかったですよね?」 「相手を傷付けるのを恐れたのではなく?」 「あ、それもありますけど」 「どうやらいい具合に知識と経験が融合しているようですね」 一歩ずつ互いに離れ、久良はスーツの乱れを直してから頭を下げる。 「大変失礼致しました。こんな短期間でそこまで先人の知恵を使いこなす器、畏れ入ります。ですがこれも全て美鈴様をお守りする役目として必要なことなので、ぜひご理解していただければ幸いです」 「は、はぁ……謝ってくれたのなら、まぁ、いいんですけど」 突然襲い掛かってきたことについては釈然としないものの、美鈴を守るテストなのだとしたら納得するしかない。何しろついこの間蜘蛛に操られた男に襲われたばかりなのだ。美鈴が今後もああいった類に襲われ続けるのだとしたら、正直あの程度の手合わせで十分なのか不安が残るぐらいだと、美緒は自分の手を握ったり開いたりする。 「それでは美鈴様、行ってらっしゃいませ」 「え、あれ、いいのですか、今ので?」 「はい、行ってらっしゃいませ」 「い、いってきます~」 美鈴もまた僅かに首を傾げながら、それでも挨拶をしたのだった。
















