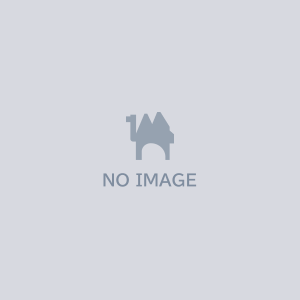組曲「ムソルグライク」~頭が良くなるクラシカル音源集~
- Digital1,980 JPY

Step into a world where the bold, earthy spirit of Mussorgsky meets the raw intensity of rock in my new album—a realm where dark Russian landscapes are electrified and emotions surge like storm-driven rivers. Imagine the dramatic power of “Pictures at an Exhibition” erupting through roaring guitars, while drums crash like thunder across desolate plains and keyboards shimmer like moonlight on icy rivers. Each track is a tapestry of grit and grandeur: melodies twist and tumble like ancient cobblestones under a winter wind, basslines throb like the heartbeat of a restless city, and vocals rise like voices echoing from a shadowed cathedral. From haunting nocturnes to wild, unrestrained dances, every arrangement captures Mussorgsky’s raw imagination while igniting it with rock’s ferocity. This album isn’t just a reinterpretation—it’s a journey into the primal and the poetic, where classical darkness meets contemporary fire. Let the music sweep you through forests of emotion, across storms of sound, and into the electrified soul of Mussorgsky, alive, untamed, and unforgettable.