恐るべき子供たち
- 支払いから発送までの日数:10日以内在庫なし物販商品(自宅から発送)¥ 300

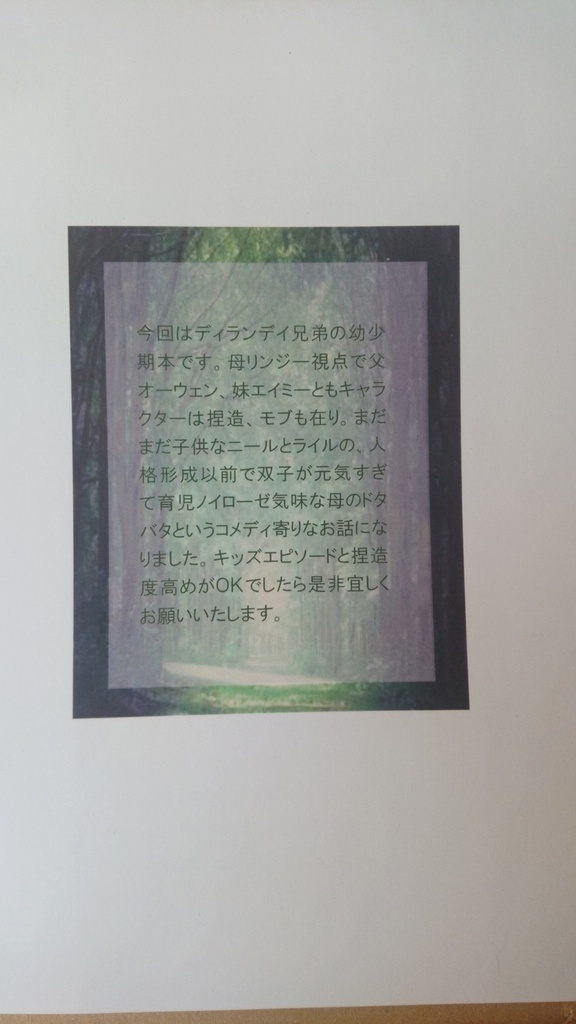
ディランディ兄弟の子供時代のお話捏造ノベルです。 2018/10/14発行 30ページ。 「あそこの双子と遊ぶんじゃありませんよ」 リンジー・ディランディは日課とする買い出し先のスーパーで流れ矢のような一言に不意打ちされた。 山と積み上げられたセールのクラッカーの箱が壁を作る向こう側で聞こえたその言葉にぎくりとしたのは彼女が双子の息子を持つ為だった以上に、地方訛の強いハスキーなその声が明らかに息子たちの遊び仲間の母親と特定出来たからだった。 「大怪我してからじゃ遅いわよ。分かったわね」 引き連れられているらしき子供の不満気にごねる声も聞こえはしたが、それらは断片のまま人混みへ消えて行った。 夫と子供たちの好物であるコルカノンの材料を揃えたカートの中に目を落とし、白い指がカートのハンドルを握りしめる。 (やっぱり・・・。) 深いため息がカートの中に積み上げられたジャガイモに降り注いだ。 (よう。あんた女の中じゃ身長高いな?) (それが何か?) (ダンスパーティーでヒール履いたら相手が居ないだろ) (失礼ね、余計なお世話、) (僕と付き合っておかないか?あんたがヒール履いても僕の方が高い。今後パートナーに困らないぜ) (・・・・・・) (しかも苦手な物理学のサポートがついてくる) その男はエメラルドグリーンの瞳をきらりと光らせて、リンジーの探していた再提出のレポート用紙をするりと机に滑らせた。 授業後の講堂は無人だ。リンジーは探し物に戻ってきた。目の前の男は、拾ったレポートの落し主を探してやってきたらしいが・・・。 (で、どう?) 週末のレクの賛否を問うような軽さで尋ねてきたきたYES・NOが、実は周到にチャンスを狙い、練りに練られた決死の文言だったことはプロポーズの時に明かされたが、その頃には見かけによらぬ小心さもすっかり掌握していた。 男はオーウェン・ディランディ、飄々とした二枚目だった学生時から年月が過ぎ、社会に出て家庭を持った現在は程好く落ち着いた三児の父であり、善き夫だった。 「そりゃお前さん、ミセス・ドネリーが親バカ なんだろ」 子供たちの寝静まった頃にオーウェンの車はガレージに滑り込む。近頃は新規事業だとかで日々忙しい。リビングで紅茶のマグカップを手にして一息つくのが憩いの時間だ。 「でも、確かにニールとライルに付き合ってたら、無茶して怪我する子はいそうだわ。その、ちょっとトロい子なんて、」 「はははは!あんたも言うねえ。確かにあいつらは相乗効果でヤンチャ度が増してるからな。トム・ソーヤの双子版だ」 「笑いごとじゃないわよ。大事になってからじゃ遅い・・・いえ、遊んでくれる子がいなくなっちゃったら、」 「いるだろ、最低一人はいつも隣に」 「そういう問題じゃないわ。子供たちにだってコミュニティってものが、」 「大丈夫だって。僕らが子供の頃と同じさ。自然に任せておけば、なるようになる」 「そうかしら」 「心配性だな、昔からだけど」 立ち上がって大きな手でリンジーの肩を撫でる。ゆったりした気配に癒されてリンジーは眉間を開いた。 「週末には裏の木、何とかしましょうね」 「大丈夫だ、この際だから何か大木になる木に植え替えよう。ツリーハウスが作れるようなやつな」 子供たちが家の裏の木に樹上基地と称して小屋を作り始めた。せいぜい腰掛け板に雨避けの屋根をつける程度の鳥小屋に毛の生えたようなものだろうと容認していたある日、かれらは居間から持ち出したソファを樹上に設置しようとロープで吊り上げ始め・・・さほどに幹も太くないその木はたちまちに根本からぼっきり折れた。樹上から落ちたライルの痣とソファに頭をぶつけたニールの瘤という軽症だったものの一歩間違えば取り返しがつかないことになっていた筈だった。 「でも、植えた木が大木になる頃にはあの子た ちはパパかおじいちゃんね」 「じゃあ孫に作らせたらいいさ」 「ふふ、」 「小さなエイミーが居て、腕白二匹は手に余るだろうねリンジー」 「大丈夫よ、冷や冷やさせられてばかりだけど私たちの宝だわ」 夫婦は小さなキスをして就寝の支度に入った。 オーウェンは明日からしばらくダブリンへ出張する。これまでにも幾度かあった事だし、夫の留守中といってもいつも通りと言えばいつも通りだ。勿論、双子のやんちゃな息子たちが事件を起こさず、妹の、まだ幼児のエイミーが突如大熱を出したりしなければ、である。 (なるようになる・・・そうよね、子供は自然にしておくのが一番、) 既に寝入っている夫と、その隣で小さな寝息を立てているエイミーのキルトケットを直して、隣の双子たちの子供部屋の物音に耳を欹てるのが癖になっている自分を笑いながら、リンジーは眠りに落ちて行った。 兄のニール、弟のライル。 ふたりを授かった時のディランディ夫妻は幸福の極みだった。生まれて来た一卵性双生児の息子たちは父の端正、母の可憐をバランスよく受け継ぎ凝縮したかのような愛くるしい容姿に健康な身体、そして高い身体能力に恵まれてすくすく元気に育った。 元気。 いや活発だった。とにかく好奇心が旺盛で行動力とバイタリティに溢れている。

