【セロ上】gift
- 支払いから発送までの日数:10日以内あんしんBOOTHパックで配送予定物販商品(自宅から発送)¥ 650
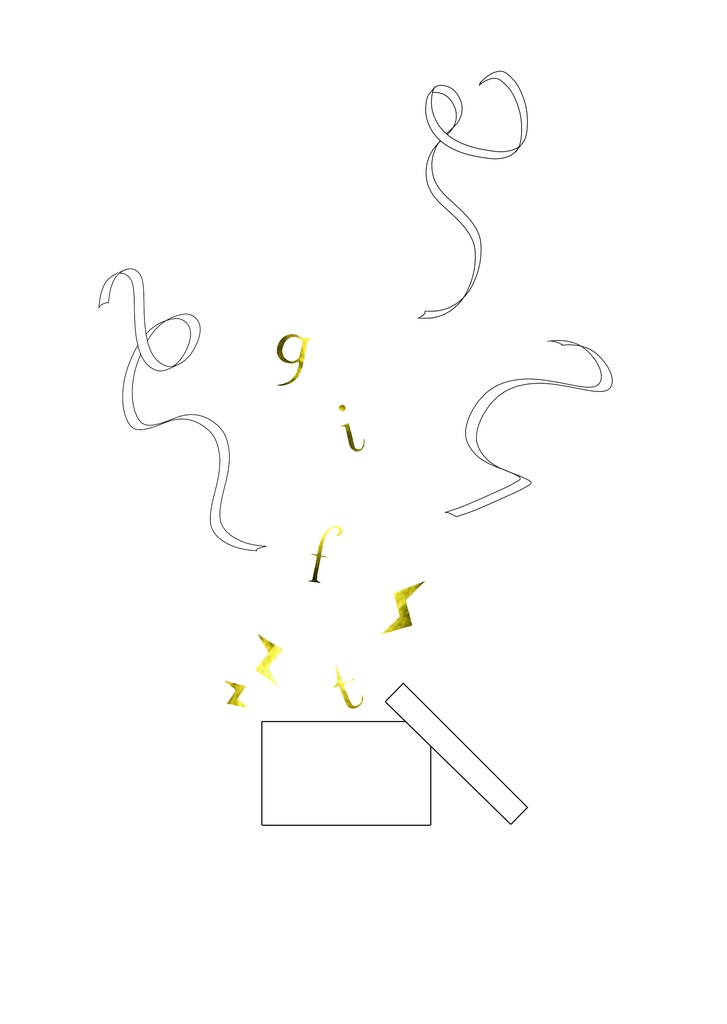
2022.7.24(日)星に願いを。2022-day2-内ハンタスティックウェイ2にて頒布いたしました新刊です。 「gift」 A5/本文48ページ/通頒680円 ※イベント頒布価格とは異なります。ご了承ください。 表紙のタイトル部分はイエロー箔が押されているのでキラキラです。 おまけとして、後日譚を書いたA7サイズの折り本をお付けします。 「他人の子を育てるせろはんた」が書きたくて書きました。 設定をお読みの上、苦手なものがひとつでもある場合はご遠慮いただけますようお願いいたします。
【セロ上】新刊「gift」
プロヒーロー設定。 かみなりくんに結婚歴あり、実子在り。 かみなりくんの奥さんの名前ガンガン出てきます。 恋愛関係ではない名前ありモブ(男女とも)との絡みあり。 セロ上というよりもセロ上になるかもしれない話。 捏造につぐ捏造、なんでも許せる人向け。 ― 冒頭 ― 「こぼしてるよ」 「ん~?」 「ほら、玉子落ちてる」 「たまごぉ?」 「あ、あ、ほら、お皿の上で食べな」 「はーい」 小さな手がぎこちなくサンドイッチを掴み、あんぐりと開いた口のわりに控えめな齧り跡を残す。その下から、むにっとはみ出した玉子サラダがぼたっと白い皿に落ちた。不格好になったサンドイッチを持ち上げて、皿を覗き込みながらもぐもぐと咀嚼し、膨らんでいた丸い頬が段々縮んでいくと、 「おちちゃったぁ」 と、小さな指がぐちゃっと落ちた玉子サラダを摘み上げた。 「またどうせ落とすんだから、最後でいいのに」 なんて言ったところで理解はできていないだろう。汚れた指を舐める前に拭き取ってやると、また先ほどと同じ光景が繰り返された。 「おっと、もうこんな時間か。さや、もう少しスピード上げて」 「んっ」 自分の皿をキッチンに運びながら急かすと、『さや』は咀嚼スピードを上げた。 「喉詰まらせないでね。牛乳も……うん。食べた?」 「ごちそーさまでした!」 パンッと顔の前で手を合わせると、満面の笑みを浮かべてそう言った。汚れた手と口をきれいにしてから、食器を一つにまとめて布巾でテーブルを拭き、キッチンに運んでさっさと洗い始めた。 「さや、靴下穿いて」 「はーい」 「いいお返事でーす」 「でーすっ」 鈴が転がるようなかわいい声が弾む。さやは床に座り小さな足先に靴下をかぶせると、きゅーっと一気に引っ張り上げた。すると、足の甲にぽっこりと現れた小さな三角の山。 「さや~、かかとが上に来ちゃってるよ~」 泡を洗い流しながら言うと、かかと?と聞き返された。何度言っても覚えられないのは、まだ四歳だからだろうか。小さな子と接したことがないから、この年齢でできることとできないことがどの程度なのかわからない。子育ての先輩に聞く度に「その頃はそんなもんよ」と笑って返されてしまい、申し訳ないがなにも参考にならなかった。 「うん。かかとは地面だよ。ちょっと待ってね」 「とーとぉ……」 「なに……あ、トイレ? 行ける?」 「はーい」 もじもじしていたわりにのんびりとしたあどけない声が返ってきて、あきれるやらホッとするやらだった。俺はコンッと水道のコックを上げると、タオルで手を拭いて登園の準備に移った。準備と言っても持ち物は前日に用意してあるから、連絡帳を入れるくらいだ。忘れ物はないかなとリュックの中をチェックしている背後から、ぱたぱたという小さな足音が、トイレから洗面所へ向かうのが聞こえた。 「とーと、おててあらってきたよ」 「よし、じゃあ行くから靴履いて」 はーいといいお返事をしたさやは、、トットットと玄関へ向かった。俺もエアコンを切って電気を消したところで、大事なルーティーンが抜けていたことに気づいた。 「あ! そうだ、さやー! 戻ってー! 行ってきますしてないよー!」 「そーだったぁ!」 さやの声と慌てて戻ってくる足音が聞こえた。 「おいで」 戻ってきたさやと、リビングの隅に置いた棚に向かって並び、おりんを鳴らすと写真立に向かって手を合わせた。 「晶さん、行ってきます」 「ままいってきまぁす」 時間にして一分程度だけれど、さやにとって大切な時間だから、俺は毎日欠かさないようにしている。 「さて、行こうか」 「はーい」 玄関先で忘れ物がないか最終確認をすると、俺たちは家を出た。 「今日もお迎え最後になるかもしれないけど、ミア先生と遊んで待っててね」 「はーい」 「はい、いいお返事」 「ぱぱのおみあいは?」 「今日はちょっと難しいから、明日の休みに行こ」 「やったぁ~♪」 にこにこのさやに、自然と俺の頬もゆるむ。握った小さな手、懸命に歩く小さな歩幅、うんと低い背。全部がまだまだ小さくて脆い、俺のことを「とーと」と呼ぶこの女の子は、俺の血縁者でもなんでもない。父親にそっくりな金髪と琥珀色の瞳を持つさやは、俺の元同級生で同じ事務所のヒーロー・チャージズマこと、上鳴電気の娘だ。 ─俺……もう…… 目の下に隈を作りひどく疲れた顔の上鳴が、この子を大切そうに抱っこしながら事務所に連れて来たのは一年以上前の雪の日だった。しんしんと降り続き、積もった雪があらゆる音を吸い取りいつもよりうんと静かな夕方。早番上がりの俺が帰り支度をしている時に、非番の上鳴は娘のさやを連れてやってきた。上鳴の妻であり、さやの母親である晶さんが病気で他界してから三カ月、上鳴は悲しみと絶望を振り払うように「俺が一人でちゃんと育てる」と、実家や義理の両親からの援助も交えつつ懸命に仕事と家事と育児をこなし続けた。 絶対に無理すんなよと何度言ってもあいつは「だいじょーぶ」と下手くそに笑った。保育園の送迎に合わせて上鳴のシフトは日勤固定になった。事務所側もバックアプしていたし、周りからの援助はそれなりにあった。それでもやっぱり、子供は母親が恋しい年齢で。 「毎日毎日、さやが泣くんだ」 事務所のソファに座り、温かいコーヒーをすすって上鳴が覇気のない声でぽつりと零した。二歳という年齢で、母親が死んだことを理解するのは難しい。不可と言ってもいいだろう。毎日毎日一緒にいた大好きな母親が突然いなくなれば、恋しく想って泣くのも当然だ。それは父親がいるとしても、きっと変わらない。父親は父親であって母親じゃない。逆もまた然りだ。ある程度育てば、脳で理解しいつしか心が追いつく。でも、この世に生を受けてたった三年しか経っていない幼子には無理な話だった。そして、上鳴は心身ともに限界を迎えた。 「俺、俺、この子のパパなのに……俺じゃ、」 「ダメじゃねぇよ」 上鳴自身が言ったら絶対にいけない言葉を俺が継ぎ、柔く否定した。たとえ逆だったとしても、この子は泣いて明け暮れるだろう。あたり前のように存在し、自分にたくさんの愛情を注いでくれた相手が突然いなくなるということは、そういうことなんだ。残った人ではどうにも埋められない。でも、だからと言って残った人じゃダメなわけじゃない。ただ違うだけで、この子にとって大切な『パパ』であることには変わらない。 「『大好きなパパ』はおまえだけだよ」 ぼんやりと俺を見上げていた金色の目が、みるみる内に膜を張り決壊した。短い眉がぎゅっと寄り唇がわななき、大粒の涙がとめどなく溢れ、上鳴はぐしゃぐしゃの泣き顔で声を殺して泣き続けた。腕の中でスヤスヤと眠る幼い娘を、そっと抱きしめながら。 俺が上鳴とさやと一緒に暮らすことを決めたのは、その日のうちだった。 「よろしくお願いします」 「はーい、お預かりしますね」 「いってらっしゃーいっ」 「行ってきます」 保育園の先生に抱っこされたままニコニコと手を振るさやに、俺もまた笑って振り返した。 あの雪の日から始まった新しい生活は、もう一年と五カ月ほど経った。最初の頃こそ俺に懐かず泣いてばかりだったさやも、俺がいることで落ち着けるようになった上鳴が余裕をもってさやに対応できるようになり、いつしか寂しさから泣くことは少なくなった。親の不安は子供に伝播する。あの頃の上鳴は、正直誰が見ても危うくて、食事もまともに摂れていないことがわかるほどに痩せていた。上鳴が憔悴している原因は、慣れない子育てだけじゃない。生涯を誓った相手と死別したんだ。自分が泣きたい立場なのに、そんな場合じゃないと両脚で立って小さな命を守り続けたんだ。メンタルがボロボロになって当然なのに、あいつは空元気だとわかるようなバレバレの作り笑顔で必死に生きていた。元々素直で嘘をつけないからこそ、その虚勢は見ていて本当に痛々しかった。 上鳴のそばにいるのは、別に俺じゃなくてもいいんだと思う。会話が成り立つ大人が家にいれば、親でも他の友達でも誰でも上鳴にとっての避難所になれると思う。俺は子供と接する機会はそれほどないから、どうしたって意識しないと子供と同じ目線に立てないし、最初の頃はさやが「できないこと」がわからなくて、何回も失敗してた。だから、俺じゃなくて上鳴のご両親と同居したらどうかと提案したことがある。そうしたらあいつは一瞬キョトンしてからう~んと唸り、それからこう答えた。 「俺は瀬呂がいい」 提案に対しての回答としてそれが正解だったのかよくわからないが、俺は予想外の答えに言葉が詰まり、腹の奥底に埋めた淡い想い出に触れられた気がして変な顔をしてしまった。俺だって上鳴じゃなかったら……いや、上鳴でもあの姿を目の当たりにしていなければ、手を差し伸べなかったと思う。誰かと暮らすことは、自分のプライベートもプライバシーもルールもすべてその誰かありきで考えなければならなくなる。互いに干渉しないと決めていてもそれはなかなか難しく、小さな子供がいればなおさらだ。でも、俺はそれら全部を飲み込んで、上鳴とさやのそばにいようと決めたんだ。友達として。激動の高校時代を一緒に過ごした、戦友として、同志として。 「はよざいまーす」 「セロファンおはようございますっ」 「今日も暑いっすね~」 「パトロール中、熱中症に気を付けてくださいね」 「水分ちゃんと摂りますよ」 夏の日差しはいつだって容赦ない。今日もまた、セロファンとしての一日が始まった。 ~中略~ 「とーと?」 「うん?」 「おげんき?」 「おもしろいこと聞くね。お元気よ?」 ベッドの中、カーテンを片側だけ開けた窓から射しこむ月光が、さやの心配そうな顔を照らした。例の漫画喫茶から事務所へ戻ると、ちょうど退勤の時間だった。決定に納得はできなかったが、近親者が事件から外されることはままあることだからと必死で自分に言い聞かせた。近親者どころか他人の俺だけれど、さやの保護者という点では家族のようなものだろう。 「難しいお顔してた?」 「うん、してた」 「そっか。ごめんね。なんでもないよ」 安心させるように一度ぎゅっと抱きしめると、さやは笑みを浮かべたまま目を瞑った。そして、俺の腕をポンポンと優しくゆっくり叩きながら、 「だいじょーぶ、だいじょーぶ」 と繰り返した。 あぁ、これは上鳴だ。 直感でそう思った。さやが不安な時や怖い夢を見て眠れない時、上鳴はきっとこうして寝かせたんだろう。落ち着かせるように、ゆっくり何度も「大丈夫」と言いながら。普段はうるさいけれど、上鳴の低い声は耳に優しい。さやに対してだったら、なおさら柔らかくなるんだろう。上鳴の優しい気持ちが、さやから俺へと渡される。さやの言葉や行動の端々に上鳴を感じる度に、あいつちゃんと父親やってんじゃんって思う。 「ありがとね」 「だいじょーぶ?」 「うん、大丈夫だよ。さやは優しいね」 頭を撫でると、嬉しそうに笑い、それから眠たそうな声で「ぱぱのまねっこなの」と言った。 「そっか」 「へへ」 「さやのおかげでグッスリできそうだな」 「さやもねむ~い」 小さなあくびをしたさやは、もぞもぞと俺のほうへ向き直して目を閉じた。 「おやすみなさぁい」 「おやすみ」 それから五分も経たないうちに、気持ち良さそうな寝息が聞こえてきた。上鳴にそっくりな寝顔を眺めながら、病室の上鳴を想う。こんないい子ほっといておまえはなにやってンのって、ちょっと腹を立てる。それから、それから……。 「……おやすみ、上鳴」 同じ月明りの下、今日も目覚めない上鳴に祈りを送った。
