この世界にふたりだけ 1
- Digital500 JPY

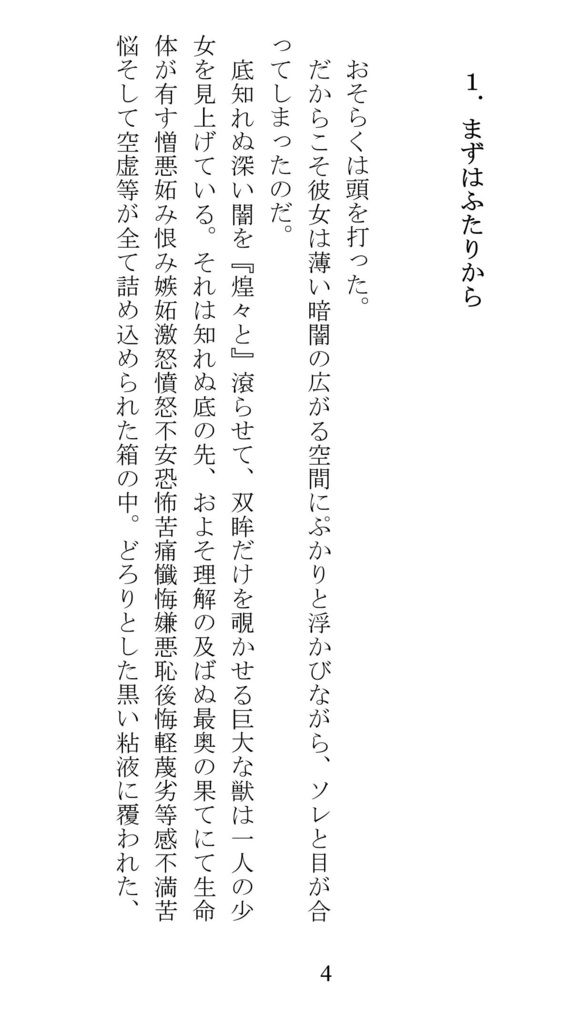


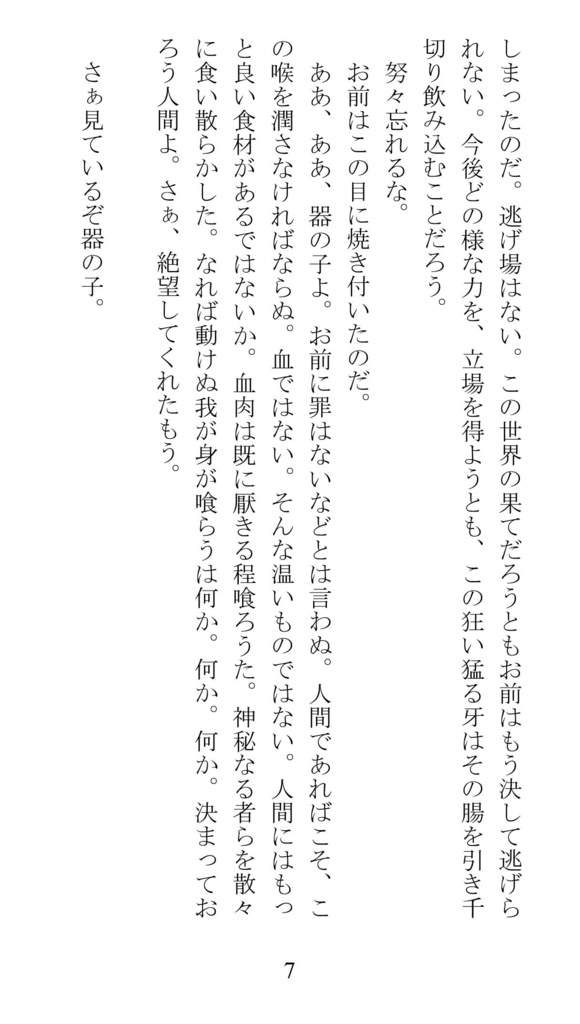
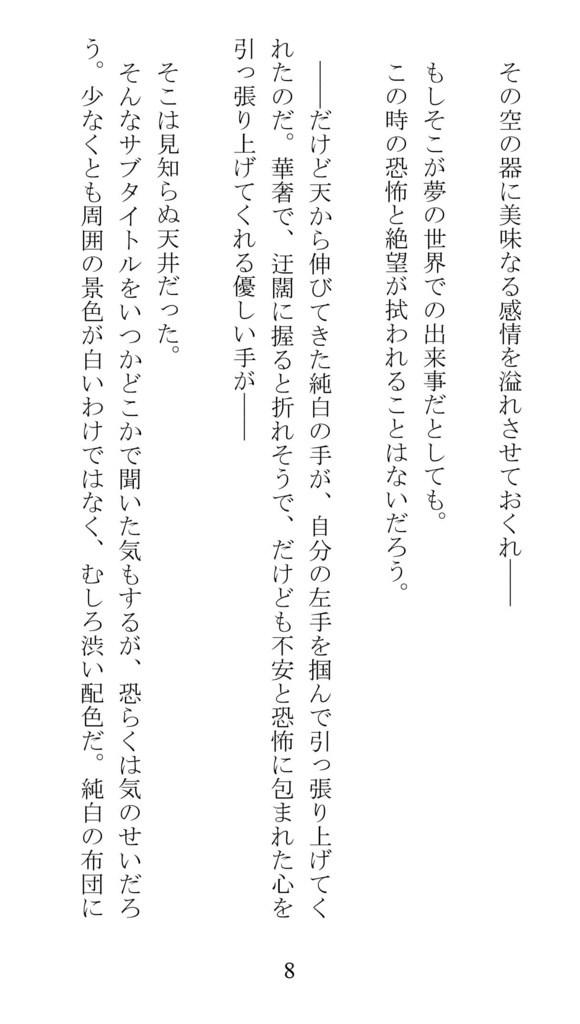
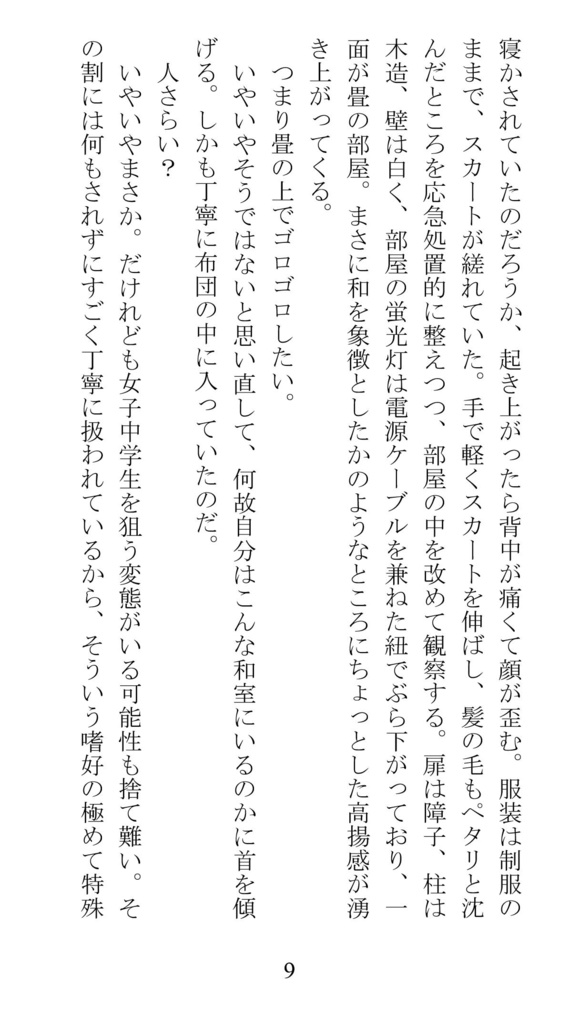
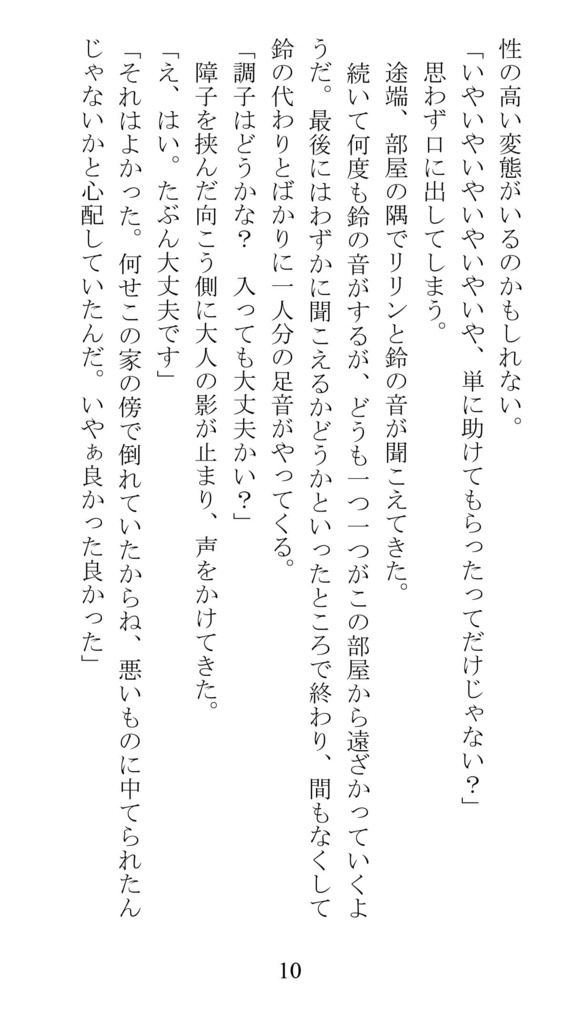
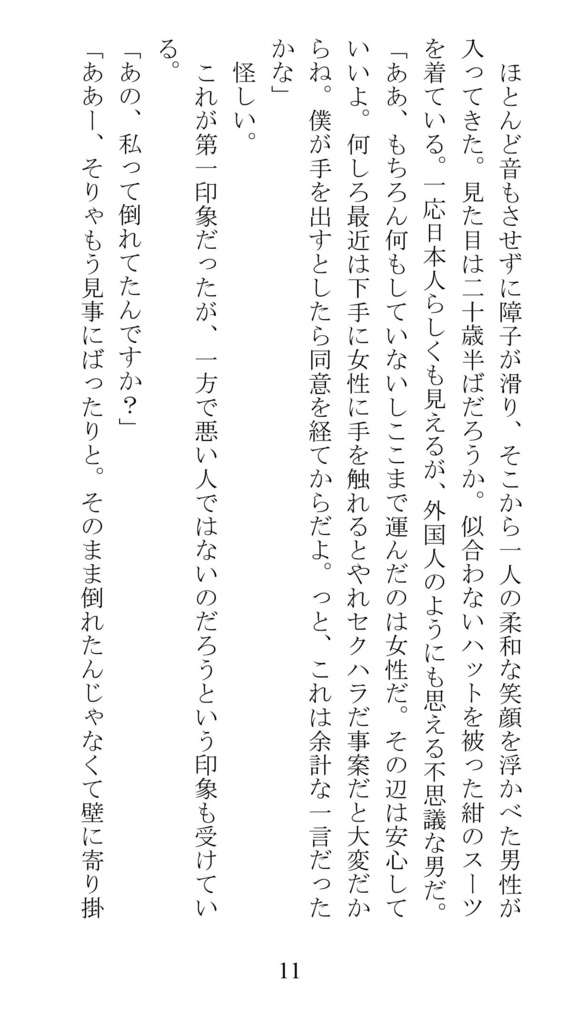
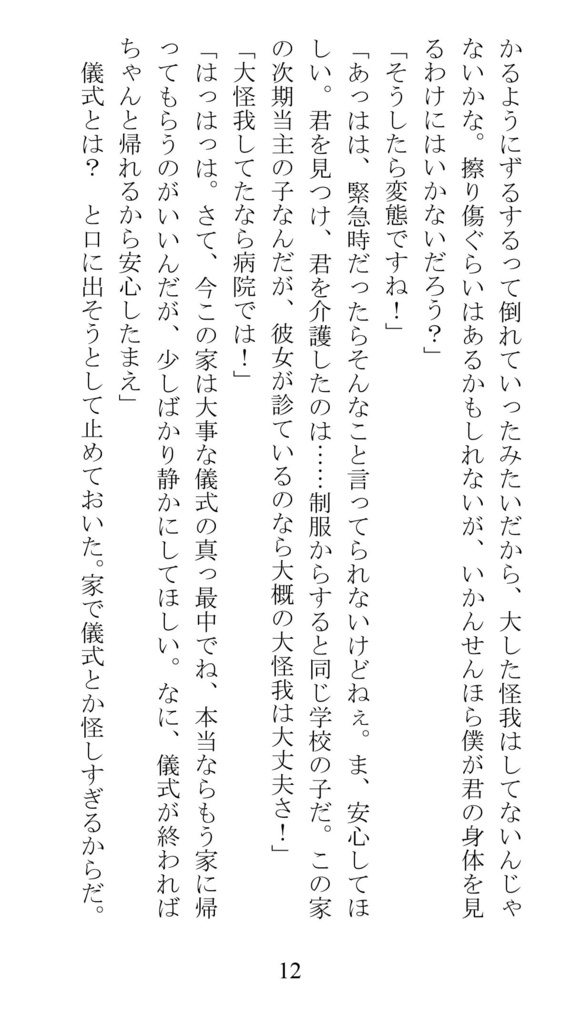
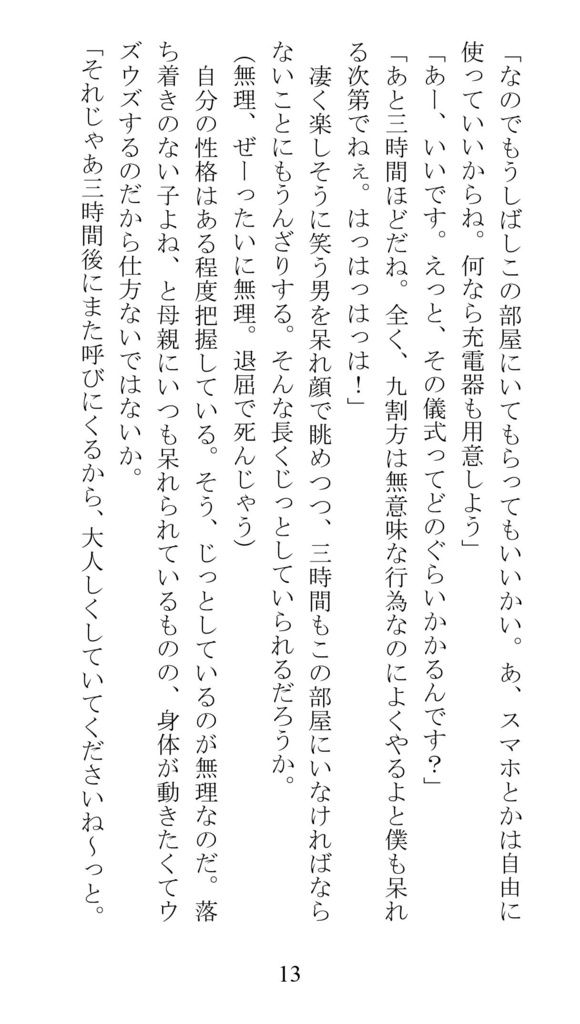
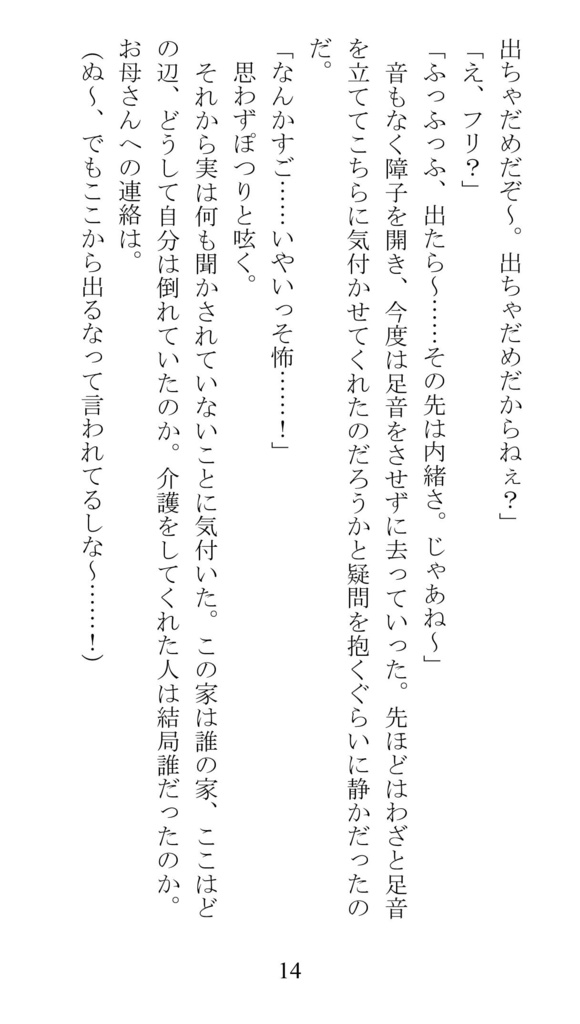
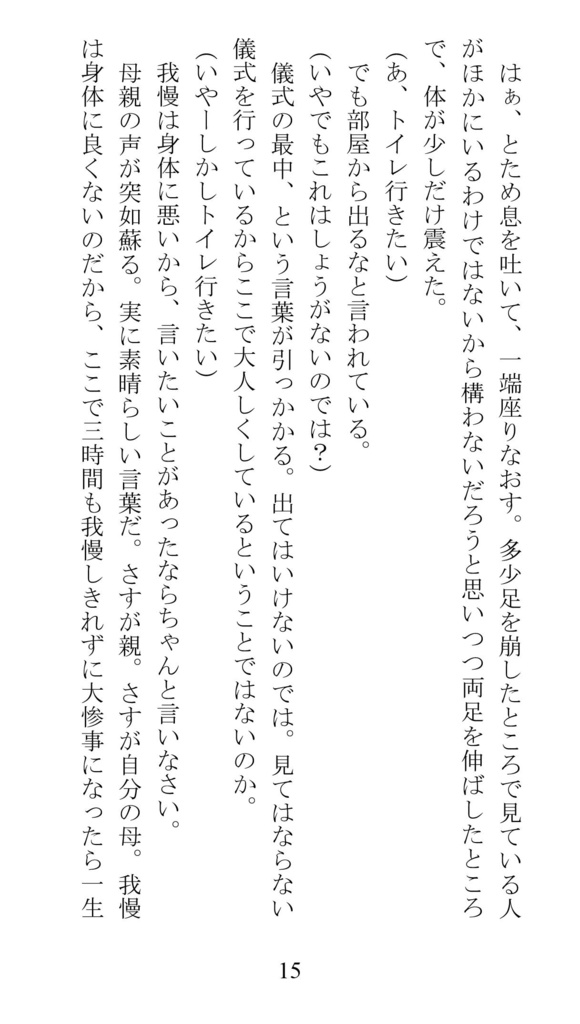
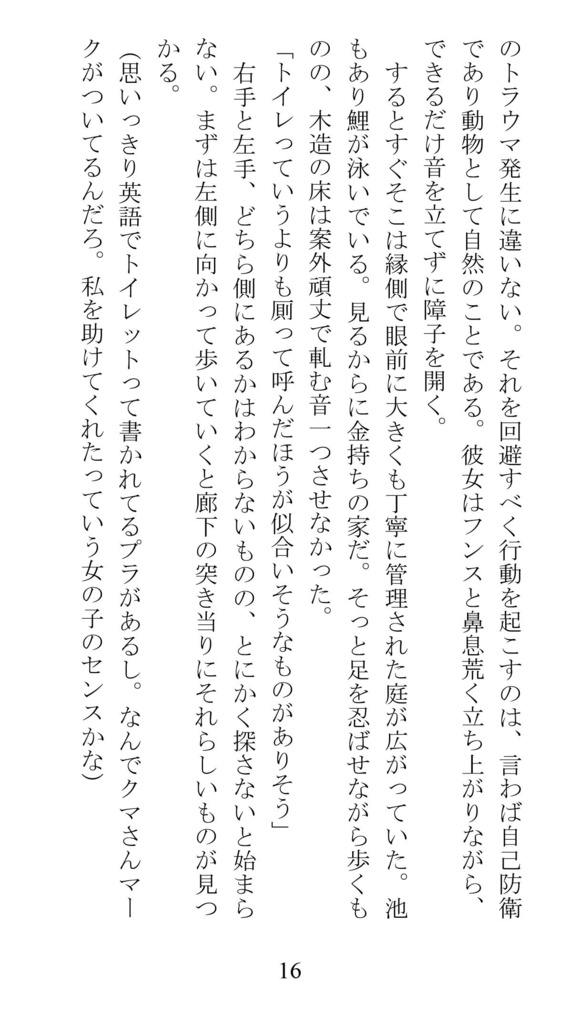
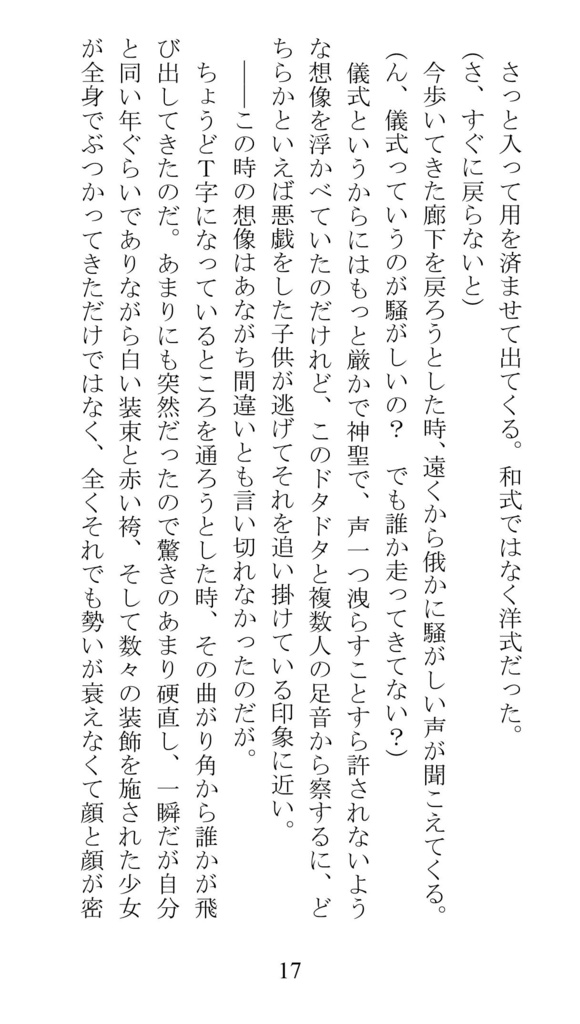



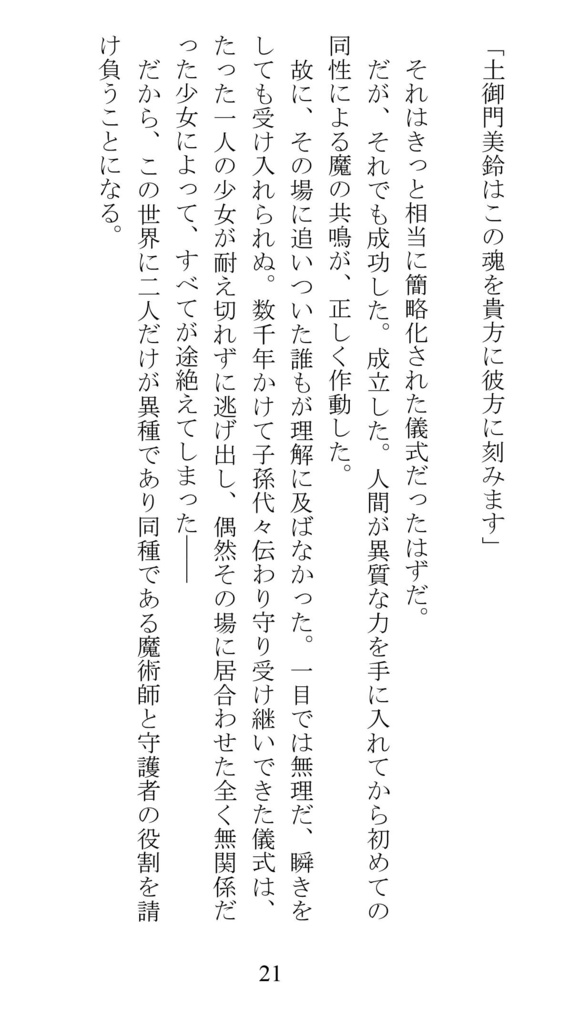
著者:平乃ひら 表紙:みちょこ ロゴ・キャラクターデザイン:みちょこ ページ数:218(表紙・裏表紙抜かす) 「土御門美鈴はこの魂を貴方に彼方に刻みます」 とある事故(キス)がきっかけで中学生夫婦となった美緒と美鈴。しかも美鈴は物理法則を無視した力、魔術を扱う特殊な家系の女の子。そんな不可思議な世界を知らず普通の女の子として育ってきた美緒は「どうしてこうなった?」と振り返る間もなくトンデモナイ事件に巻き込まれていく……! ――それはやがて世界を救うことになる物語の始まりで。 でもまだ二人は唐突に決まった夫婦の関係に戸惑うばかり―― 中学生百合夫婦伝奇ストーリー・開幕――!
1.まずはふたりから
おそらくは頭を打った。 だからこそ彼女は薄い暗闇の広がる空間にぷかりと浮かびながら、ソレと目が合ってしまったのだ。 底知れぬ深い闇を『煌々と』滾らせて、双眸だけを覗かせる巨大な獣は一人の少女を見上げている。それは知れぬ底の先、およそ理解の及ばぬ最奥の果てにて生命体が有す憎悪妬み恨み嫉妬激怒憤怒不安恐怖苦痛懺悔嫌悪恥後悔軽蔑劣等感不満苦悩そして空虚等が全て詰め込められた箱の中。どろりとした黒い粘液に覆われた、たった一匹の獣を閉じ込める最悪の檻。希望も何も通さぬはずのそこからは、しかして人より巨大な眼だけが一人の少女を見据えていたのだ。それは単なる興味本位か、あるいはただ鬱陶しい小虫を視線のみで追い払おうとしているだけか。 一つだけ言えることがある。 人は ここに 居てはならない。 ここは最悪の果て。最古の獣の檻。終焉を告げる刻の牙が世界というシステムを喰らう場所。 その檻があればこそ世界は、この世は存続を赦されている。獣はそこに存在しているだけに過ぎずに在る。 だが、だがしかし、決して忘れてはならない。その檻は未来永劫続くような錯覚を与えるが、そうではない。忘れてしまった人々は思い出さなければならない。神話の獣を。神を喰ろうた黒き獣を。獣は未だに喰らい足りぬ。獣は未だに世界に栄える人間を見据えている。獣は己を縛る六つの拘束と叫びの檻を赦さず、生命を喰らい足りず、海を創造するかのような口元からの唾液は永劫の闇の底へと落ちていく。 ただ何の取柄もないはずの少女は、改めてその獣と目が合ってしまったことに恐怖を覚え、震えることも目を逸らすことも許されず、彼の者の姿を脳裏に焼き付けた。目を逸らした瞬間に魂が離れていくかのような死への恐怖、指先を動かした瞬間に魂ごとあの牙に喰らわれるかのような絶望。汗一滴すら動いてはならぬ。あの獣は人間の発するあらゆる動き、感情を胎の中に収め、その上で足りぬと吠える最悪の獣だ―― ああ、ああ、見ているぞ。お前が見えているぞ。このマナコにしかと焼き付けて、そして妬き付けているぞ。お前は気付いたのだ。お前は見てしまい、そして見えてしまったのだ。逃げ場はない。この世界の果てだろうともお前はもう決して逃げられない。今後どの様な力を、立場を得ようとも、この狂い猛る牙はその腸を引き千切り飲み込むことだろう。 努々忘れるな。 お前はこの目に焼き付いたのだ。 ああ、ああ、器の子よ。お前に罪はないなどとは言わぬ。人間であればこそ、この喉を潤さなければならぬ。血ではない。そんな温いものではない。人間にはもっと良い食材があるではないか。血肉は既に厭きる程喰ろうた。神秘なる者らを散々に食い散らかした。なれば動けぬ我が身が喰らうは何か。何か。何か。決まっておろう人間よ。さぁ、絶望してくれたもう。 さぁ見ているぞ器の子。 その空の器に美味なる感情を溢れさせておくれ―― もしそこが夢の世界での出来事だとしても。 この時の恐怖と絶望が拭われることはないだろう。 ――だけど天から伸びてきた純白の手が、自分の左手を掴んで引っ張り上げてくれたのだ。華奢で、迂闊に握ると折れそうで、だけども不安と恐怖に包まれた心を引っ張り上げてくれる優しい手が―― そこは見知らぬ天井だった。 そんなサブタイトルをいつかどこかで聞いた気もするが、恐らくは気のせいだろう。少なくとも周囲の景色が白いわけではなく、むしろ渋い配色だ。純白の布団に寝かされていたのだろうか、起き上がったら背中が痛くて顔が歪む。服装は制服のままで、スカートが縒れていた。手で軽くスカートを伸ばし、髪の毛もペタリと沈んだところを応急処置的に整えつつ、部屋の中を改めて観察する。扉は障子、柱は木造、壁は白く、部屋の蛍光灯は電源ケーブルを兼ねた紐でぶら下がっており、一面が畳の部屋。まさに和を象徴としたかのようなところにちょっとした高揚感が湧き上がってくる。 つまり畳の上でゴロゴロしたい。 いやいやそうではないと思い直して、何故自分はこんな和室にいるのかに首を傾げる。しかも丁寧に布団の中に入っていたのだ。 人さらい? いやいやまさか。だけれども女子中学生を狙う変態がいる可能性も捨て難い。その割には何もされずにすごく丁寧に扱われているから、そういう嗜好の極めて特殊性の高い変態がいるのかもしれない。 「いやいやいやいやいやいや、単に助けてもらったってだけじゃない?」 思わず口に出してしまう。 途端、部屋の隅でリリンと鈴の音が聞こえてきた。 続いて何度も鈴の音がするが、どうも一つ一つがこの部屋から遠ざかっていくようだ。最後にはわずかに聞こえるかどうかといったところで終わり、間もなくして鈴の代わりとばかりに一人分の足音がやってくる。 「調子はどうかな? 入っても大丈夫かい?」 障子を挟んだ向こう側に大人の影が止まり、声をかけてきた。 「え、はい。たぶん大丈夫です」 「それはよかった。何せこの家の傍で倒れていたからね、悪いものに中てられたんじゃないかと心配していたんだ。いやぁ良かった良かった」 ほとんど音もさせずに障子が滑り、そこから一人の柔和な笑顔を浮かべた男性が入ってきた。見た目は二十歳半ばだろうか。似合わないハットを被った紺のスーツを着ている。一応日本人らしくも見えるが、外国人のようにも思える不思議な男だ。 「ああ、もちろん何もしていないしここまで運んだのは女性だ。その辺は安心していいよ。何しろ最近は下手に女性に手を触れるとやれセクハラだ事案だと大変だからね。僕が手を出すとしたら同意を経てからだよ。っと、これは余計な一言だったかな」 怪しい。 これが第一印象だったが、一方で悪い人ではないのだろうという印象も受けている。 「あの、私って倒れてたんですか?」 「ああー、そりゃもう見事にばったりと。そのまま倒れたんじゃなくて壁に寄り掛かるようにずるするって倒れていったみたいだから、大した怪我はしてないんじゃないかな。擦り傷ぐらいはあるかもしれないが、いかんせんほら僕が君の身体を見るわけにはいかないだろう?」 「そうしたら変態ですね!」 「あっはは、緊急時だったらそんなこと言ってられないけどねぇ。ま、安心してほしい。君を見つけ、君を介護したのは……制服からすると同じ学校の子だ。この家の次期当主の子なんだが、彼女が診ているのなら大概の大怪我は大丈夫さ!」 「大怪我してたなら病院では!」 「はっはっは。さて、今この家は大事な儀式の真っ最中でね、本当ならもう家に帰ってもらうのがいいんだが、少しばかり静かにしてほしい。なに、儀式が終わればちゃんと帰れるから安心したまえ」 儀式とは? と口に出そうとして止めておいた。家で儀式とか怪しすぎるからだ。 「なのでもうしばしこの部屋にいてもらってもいいかい。あ、スマホとかは自由に使っていいからね。何なら充電器も用意しよう」 「あー、いいです。えっと、その儀式ってどのぐらいかかるんです?」 「あと三時間ほどだね。全く、九割方は無意味な行為なのによくやるよと僕も呆れる次第でねぇ。はっはっはっは!」 凄く楽しそうに笑う男を呆れ顔で眺めつつ、三時間もこの部屋にいなければならないことにもうんざりする。そんな長くじっとしていられるだろうか。 (無理、ぜーったいに無理。退屈で死んじゃう) 自分の性格はある程度把握している。そう、じっとしているのが無理なのだ。落ち着きのない子よね、と母親にいつも呆れられているものの、身体が動きたくてウズウズするのだから仕方ないではないか。 「それじゃあ三時間後にまた呼びにくるから、大人しくしていてくださいね~っと。出ちゃだめだぞ~。出ちゃだめだからねぇ?」 「え、フリ?」 「ふっふっふ、出たら~……その先は内緒さ。じゃあね~」 音もなく障子を開き、今度は足音をさせずに去っていった。先ほどはわざと足音を立ててこちらに気付かせてくれたのだろうかと疑問を抱くぐらいに静かだったのだ。 「なんかすご……いやいっそ怖……!」 思わずぽつりと呟く。 それから実は何も聞かされていないことに気付いた。この家は誰の家、ここはどの辺、どうして自分は倒れていたのか。介護をしてくれた人は結局誰だったのか。お母さんへの連絡は。 (ぬ~、でもここから出るなって言われてるしな~……!) はぁ、とため息を吐いて、一端座りなおす。多少足を崩したところで見ている人がほかにいるわけではないから構わないだろうと思いつつ両足を伸ばしたところで、体が少しだけ震えた。 (あ、トイレ行きたい) でも部屋から出るなと言われている。 (いやでもこれはしょうがないのでは?) 儀式の最中、という言葉が引っかかる。出てはいけないのでは。見てはならない儀式を行っているからここで大人しくしているということではないのか。 (いやーしかしトイレ行きたい) 我慢は身体に悪いから、言いたいことがあったならちゃんと言いなさい。 母親の声が突如蘇る。実に素晴らしい言葉だ。さすが親。さすが自分の母。我慢は身体に良くないのだから、ここで三時間も我慢しきれずに大惨事になったら一生のトラウマ発生に違いない。それを回避すべく行動を起こすのは、言わば自己防衛であり動物として自然のことである。彼女はフンスと鼻息荒く立ち上がりながら、できるだけ音を立てずに障子を開く。 するとすぐそこは縁側で眼前に大きくも丁寧に管理された庭が広がっていた。池もあり鯉が泳いでいる。見るからに金持ちの家だ。そっと足を忍ばせながら歩くものの、木造の床は案外頑丈で軋む音一つさせなかった。 「トイレっていうよりも厠って呼んだほうが似合いそうなものがありそう」 右手と左手、どちら側にあるかはわからないものの、とにかく探さないと始まらない。まずは左側に向かって歩いていくと廊下の突き当りにそれらしいものが見つかる。 (思いっきり英語でトイレットって書かれてるプラがあるし。なんでクマさんマークがついてるんだろ。私を助けてくれたっていう女の子のセンスかな) さっと入って用を済ませて出てくる。和式ではなく洋式だった。 (さ、すぐに戻らないと) 今歩いてきた廊下を戻ろうとした時、遠くから俄かに騒がしい声が聞こえてくる。 (ん、儀式っていうのが騒がしいの? でも誰か走ってきてない?) 儀式というからにはもっと厳かで神聖で、声一つ洩らすことすら許されないような想像を浮かべていたのだけれど、このドタドタと複数人の足音から察するに、どちらかといえば悪戯をした子供が逃げてそれを追い掛けている印象に近い。 ――この時の想像はあながち間違いとも言い切れなかったのだが。 ちょうどT字になっているところを通ろうとした時、その曲がり角から誰かが飛び出してきたのだ。あまりにも突然だったので驚きのあまり硬直し、一瞬だが自分と同い年ぐらいでありながら白い装束と赤い袴、そして数々の装飾を施された少女が全身でぶつかってきただけではなく、全くそれでも勢いが衰えなくて顔と顔が密着する。 「きゃ――」 「うわ――」 悲鳴を上げることはもちろん咄嗟に避ける間すらなく、互いの唇が触れ――押し付けられ。 (んぐっ、舌まで入ってる!) さらには支えきれずに庭へと落ちる格好となったが、その瞬間に世界が止まった。口から喉を伝って身体が熱くなり、全身隈なくすべての細胞が歓喜に震えているような気さえしてくるし、何より状況を察する頭の回転速度に驚かされる。瞬間だ、その瞬間に彼女は自分の目の見える範囲全てを瞬時に把握したのだ。 (え?) 正確には止まっているわけではない。世界は――少なくともぶつかってきた少女を抱きしめる形で庭へと落ちようとしている速度は全く変わらないのだが、不思議と『結構余裕があるな』という認識を覚えたのだ。落下する身体の位置を変え、少女の足に手を伸ばして抱きかかえて余裕を持って着地する。 「は?」 自分で自分に思い切り疑問を投げ掛ける。運動は得意だが今のはアクロバティックにも程があった。単に身体を動かすのが得意な同世代で落ちながら身体の向きを変えて、少女をお姫様抱っこする芸当が可能な中学生が世界に何人いるだろうとすら考えてしまった。 抱えられている巫女装束の少女が自分を見上げているが、その顔も唖然としたものだった。よくよく観察してみると巫女というよりも花嫁衣装に近いのかもしれない。儀式的な意味合いが強い恰好なので、事情を知らないからには判断がまったくつかないけども。 「あの!」 青を真っ赤にした少女がこちらの瞳を覗き込んでくる。 「な、名前、名前を教えてください!」 「え、え、名前?」 「早く!」 「か、篭山美緒だけど」 「……篭山美緒さん……ごめんなさい、本当にごめんなさい……貴女の一生を奪うことになってごめんなさい……」 「ふぇっ! そ、そりゃさっきのは初めてのキスだったけども! あ、いやそりゃ初めてで女子同士で色々と思うところはあるけれどハプニングみたいなものだったし、いっそノーカンで」 だけれども少女は首を一度だけ横に振る。 「土御門美鈴はこの魂を貴方に彼方に刻みます」 それはきっと相当に簡略化された儀式だったはずだ。 だが、それでも成功した。成立した。人間が異質な力を手に入れてから初めての同性による魔の共鳴が、正しく作動した。 故に、その場に追いついた誰もが理解に及ばなかった。一目では無理だ、瞬きをしても受け入れられぬ。数千年かけて子孫代々伝わり守り受け継いできた儀式は、たった一人の少女が耐え切れずに逃げ出し、偶然その場に居合わせた全く無関係だった少女によって、すべてが途絶えてしまった―― だから、この世界に二人だけが異種であり同種である魔術師と守護者の役割を請け負うことになる。


















