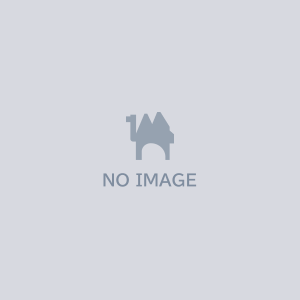sound note 室井康雄 2章 アニメーター編
- Digital1,500 JPY

アニメ私塾の室井康雄さんオーディオブック「SOUND NOTE」。 1章 少年時代編 52分 2章 アニメーター編 1時間7分 3章 アニメ私塾 ビジネスモデル構築編 41分 4章 サロン運営編 38分 SOUND NOTE アニメ私塾 室井康雄 オーディオブック 第2章 アニメーター編 67分 レビュー 文=山井淳生 第2章 アニメーター編 「今の仕事が資本になる」 少年時代編に続くアニメーター編である。アニメスタジオの最高峰、スタジオジブリに入社した室井は「動画という仕事において、同期で一番下手」だった。その挫折は、昨今の目覚ましい活躍を知る我々にとって、意外な事実である。この章では、その実際、そしてスタジオジブリ以降の室井の仕事を追う。 「下積み時代のお家賃いくらでしたか?」今回の最初の質問がこれだった。すごい。本当にすごい。徹底して、誰も聞かない(聞けない)ようで、しかし関心度の高い質問を最初に投げてくる。前章の最初の質問「どのくらいの時から、絵が好きでしたか?」の衝撃は先述したとおりだが、そのさらに上をゆくような質問だ。 家賃に続いて、当時室井が住んでいた場所も、手取りの初任給も明かされる。こんな質問が飛び交うインタビューもなかなかないだろう。いずれもここに書くのは憚られる内容なので、ぜひ本編で確認してほしいところだ。 筆者自身、来年からアニメ業界に進む大学四年生であるから、周囲にも2021年卒のアニメ業界人のたまごが何人もいる。そして彼ら彼女らと集まったときに最近決まって話題になるのが、どこらへんの、家賃いくらの家に住むか、である。十年以上前の、しかもスタジオジブリの新卒の事例とは言えど、多くの学生が興味を寄せる話題であること間違いない。 それに引き続いて、スタジオジブリの新人育成の体制やメンバーも明かされる。こちらは、アニメーターを目指す人やアニメ業界に進む人だけでなく、多くのアニメファンも気になる内容なのではないだろうか。 他方、当時、アニメ監督を志していた室井が、ひとつの通過点として捉えていた動画の仕事は、スタジオジブリにおいては特に、いち職人としての技術や忍耐を必要とするものだった。自主制作アニメで全工程を扱っていた室井にとって、それはもどかしいものでもあったし、必ずしも自身の性格に合うものでもなかった。 1年9ヶ月の在籍ののち、退職の道を選択するが、その理由を改めて問われると、室井は「迷惑をかけているのはなんとなくわかるわけですよ」と切り出した。給料分の仕事を出来ていないという自覚、迷惑をかけてクオリティを下げているのだという実感。聴いているだけで、こちらも苦しくなるような告白だった。 そして、ジブリを退職した室井に対する中武の問いにもまた、度肝を抜かれた。「どうですか。フリーになったら自由になれましたか」だ。いやあ、すごい。あまりネタを明かしすぎるのもよくないだろうから、この答えは本編を楽しみにしてもらいたい。 フリーランスのアニメーターとなった室井は『電脳コイル』や『亡念のザムド』といったタイトルに、今度は原画マンとして参加し、その腕を認められていくが、スタジオジブリの動画時代に培われた技術や、仕事へ対する心構えが、その資本となっていることに気づく。ここで室井は「今の仕事をむちゃくちゃがんばって、それを資本にして、次にもっといい仕事を得る」という仕事への姿勢を語り、中武も大いに賛同する。これも、聞き逃してはならないスタンスだろう。 筆者が雑誌取材でお話を伺ったプロデューサー、アルバイトでお世話になった制作デスク、ありとあらゆるすごい人から、軒並み同じフレーズを耳にした。若いうちは、とにかく来た球を全力で打ち返せと。このスタンス自体は、アニメでない仕事にも共通するものだろう。繰り返し肝に銘じたい言葉である。 第2章はシリーズ内でも最長となる67分の尺で、内容も盛りだくさんだ。押山清高や浅野直之といった同世代のアニメーターとの交流の話も必聴だし、サンライズやライデンフィルム京都スタジオなどのアニメ会社で新人育成を担った経験が「第3章 アニメ私塾編」につながっていくのも興味深い。 そのなかでもとりわけ最後に紹介したいのが、アニメーターは仲間内を相手に仕事をしてしまいがちで、お客さんが見えなくなってくる、という問題提起だ。それで腕を高め合うのはいいけれど、そればかりにハマってしまうのはサービス業として違うんじゃないか、と室井は続ける。 この問題はアニメーターの意識に限った話ではなく、日本のアニメ産業全体に共通してある問題だと筆者は考えるが、ここで注目したいのは、室井がアニメーターという仕事を「サービス業」と定義している点だ。きっとこれは、その定義によって答えの分かれる話で、職人的に絵の技術を高めることを是とする意見も多くあるだろう。 もっと単純な話に置き換えてしまえば、アニメづくりにおいて、クリエイティブに重きを置くか、その商業性に重きを置くかということだと思うし、その二者のせめぎ合いの末に、魅力あふれるアニメが誕生していることもわかる。しかし現状の、どこか内に向きがちな感覚、外に開かれていない感覚を、どうしてもよしとは思えないのだ。 このインタビューはあくまで「室井康雄 オーディオブック」であるため、相手(お客さん)の姿が直接見える教育に室井の関心が移っていく、という方向へ話が進む。二者択一でないこの議題は、視聴者に投げられた問いとも言えるだろう。筆者自身も、これから煮詰めていきたいテーマだ。