名告
- Ships within 10 days1 left in stockShips by Anshin-BOOTH-PackPhysical (direct)200 JPY
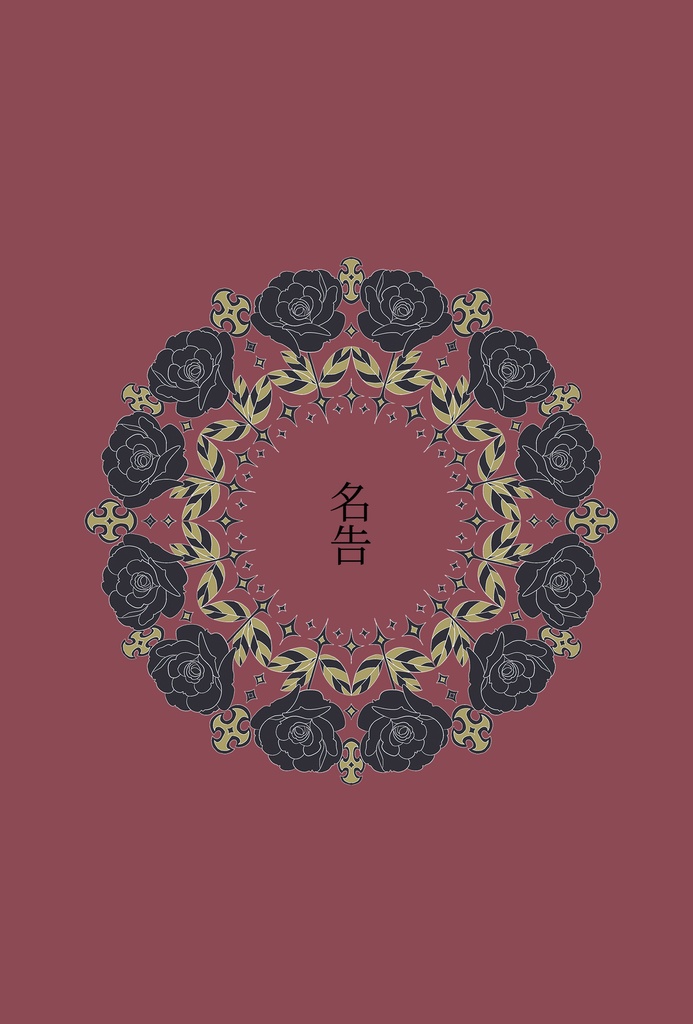
A6/30p(2022年12月発行) オズに名前を呼ばれることに執着するミスラの話。 ※一部Web上に掲載していた話を再録。 【サンプル】 最強の魔法使い、オズ──その名を知らない者はこの世界にもはや存在しないのだろう。天候すら操るというその桁外れの強さは他の国にも伝わり、人々を恐怖させていると言う。 いずれは、彼が世界を支配するのでは、とも。 そしてミスラは、そんな彼を超えて世界最強の魔法使いになる予定の男だった。きっと誰よりも強い魔法使いになるとチレッタが言ったのだ。ミスラが世界一になれないはずがない。 ただ、ミスラの名は北の国では通用しても、それ以外ではまだまだ知られていなかった。つまり、オズほどの知名度はない。 と言っても、ミスラはその点についてさほど気にしてはいなかった。どうせ、オズを殺して自分が自他共に認める最強の魔法使いとなれば、この名が世界中に知れ渡るのはわかりきっていたからだ。 しかしそれでも、ミスラの名を知っていてもらわなくては困る存在が一人だけいる。──オズだ。 ミスラに石にされてしまえば何の意味もなくなるとは言え、彼を殺し、最強の魔法使いとなる男の名くらい知っていてもらわなくては。 ミスラがオズに挑むようになってもう数年だ。北の魔法使いが生きる年月を考えれば、たったそれだけと言えばそれだけだが、何度もしつこく顔を合わせている相手の名を覚えるには十分な年月だろう。ところが、ミスラは未だにオズに対して名乗りを上げることすらできていなかった。そんな間すら与えずに呪文を唱え、ミスラを物理的に城から追い出すのがオズなのだ。 それ故、ミスラはオズと言葉を交わしたことがない。互いに聞いたことがあるのは呪文だけ、交わしたことがあるのは攻撃魔法だけだ。そうなると、他者に一切の関心を抱いていない様子のオズがミスラの名 前など知るはずもなく。 そのため、ミスラのひとまずの目標は、彼の攻撃魔法に耐え、少なくとも名乗りを上げるところまでは粘るというものだった。チレッタにそれを言ったら腹を抱えて爆笑されたが、「そういうあんたも健気でかわいくていいじゃない」とのことだったので、癪ではあるが当面はこの方向でいいのだと思う。勿論、最終的な目標は彼を殺して石にすることだ。 実際、自分の名を覚えてもらうまでは、相手に死なれては困るとミスラは思い始めていた。それまでは殺すに殺せない、と。 ミスラとて、これまで殺す相手の名前など認識していたことはない。だが、だからこそオズに名もなき有象無象として石にされた雑魚と同列には扱われたくないという思いがあり。 (くっ、今日こそ……!) オズの放つ雷を防ぎながら、ミスラは鉄の味のする唇を舐めた。今日も今日とて出会い頭に強烈な一撃をお見舞いされ、容赦のない追撃が続いている。それに耐えられるようになっただけでも大きな成長ではあったが、ミスラの第一目標はそこより少し先にあった。 オズの攻撃魔法への対処法は、ひたすら受け流すに限るのだと学んだのは一体いつ頃だったか。オズの魔法を防ぐのは今のミスラには不可能だ。そして、攻撃を上手く避け続けようとすれば目標位置を少しずつずらした連続攻撃の雨が降りだすため、それもまた得策とは言えない。ならば、攻撃を上手く受け流すのが一番早い。ミスラはオズの攻撃を食らいつつ、その威力を器用に分散させていく。受け流してもなお、気を失いそうなほどの衝撃と痛みに教われるのだから、本当に化け物みたいな男だといえるだろう。 痛みは決して好きではなかったが、オズから与えられる痛みは、彼の攻撃を受けてなお自分は生きているのだと実感させてくれるから、なんだかやけに興奮した。実際、彼とこれほどやり合って石にされない魔法使いなど、自分くらいのものではないのか。 「《ヴォクスノ》──」 「……っ《アルシム》!」 オズが次の魔法を繰り出す前に、彼の手元の杖に向かって魔法を放つ。それで魔道具を吹き飛ばせることができればよかったが、長い杖は僅かに揺れただけだった。ただ、それでも少しの隙にはなる。隙を狙ったとしてこちらの攻撃は届かないかもしれないが、声を届けることくらいはできるはずで。 「俺の名は、ミスラです。死の湖のミスラ──あなたを殺す男の名前ですよ」 覚えておいてください、とミスラはいくらか早口になりながら、一息でそう名乗りを上げた。オズの紅の眼差しが、訝しげにミスラを見つめる。出会ってから初めて彼が自分を見たようなそんな気すらして、言いようのない興奮が背筋を這い上がっていくのをミスラは感じた。 先程までの攻撃の激しさとは打って変わった、凪いだ瞳が真っ直ぐにミスラを捕える。それだけのことが胸をざわつかせるのは何故なのだろう。 しばらくの沈黙の後、オズは静かに口を開いた。また攻撃が再開されるのかと思って身構えたミスラはしかし、彼の地を這うような低い声が紡いだ言葉に固まってしまって。 「……知っている。大魔女チレッタの弟子だろう」 知っている──つまり、オズがミスラをとっくに認識していたという事実に、ミスラはわけもわからず心が震えるのを感じた。それは、初めて自分よりも格上の魔法使いを殺して石にしたときの感覚に似ていたかもしれない。 あくまでチレッタの名に付随する形で記憶されているのはわかっている。だが、それでも彼が自分の名を知っているというだけで今は十分だった。オズが名を知る魔法使いなど、この世界に一体どれほどいるだろう。恐らくその数は、多く見積もっても両手で足りる程度であるはずで。 「は、いつから……?」 「最初から、だ。立ち去れ──ミスラ」 オズの口から吐き出された自分の名に、ミスラが目を見開いたのは言うまでもない。たった三文字のその音にそこまでの意味を見出だしたことはなかった。しかし、それが彼の低い声で紡がれると、何か特別なもののようにも思われるのだから不思議な話。 チレッタに名を呼ばれたときのくすぐったさや心地よさとはまた違う、何か全身の血がかっと熱くなるような、これまでに経験したことのない感覚がミスラを襲っていた。ああ、この男を屈服させてめちゃくちゃにしてみたい──そんな欲がミスラの中に芽生え、少しずつ膨らんでいく。 しかし、ミスラはまだようやく彼に対して名乗りを上げることができたような状態。恐らく、オズを跪かせることができる日がやって来るとしても、それが何百年後何千年後になるのだろうことは本能的にわかっていた。 「はは、今日は気分がいいのでこの辺で帰ってあげます」 「……二度と来るな」 「それは無理ですよ。これでようやく、心置きなくあなたを殺せるんですから」 「…………できるものなら、やってみるがいい」 会話というにはあまりにも束の間のやり取り。だが、オズとたった数十秒言葉を交わしただけで、ミスラの胸は酷く満たされていた。今なら、最強の魔法使いだって殺せてしまいそうな気分だった。無論、今それをするつもりはないのだけれど。 ミスラは、空間魔法で扉を作ると、宣言通りその場から立ち去ることにする。どうせ、オズに挑む機会はいくらでもあるのだ。それに、彼を石にするのは、その口が自分の名を紡ぐのをもう何度か聞いてからでも遅くはない。 「それじゃあ、また来ますね。オズ」 ミスラはそう言って去り際に笑うと、オズの険しい顔に見送られながら唇を舐めた。オズとの決着はついていない。それどころか、未だ圧倒的にミスラの劣勢だ。だが、今日はそんなことも気にならないくらいに気分がよかった。 ──ボロボロであるにもかかわらず珍しく上機嫌で帰ったミスラを見て、「あんたが世界一に近付いた記念に、今夜は祝杯を上げようか!」とチレッタがはしゃいだおかげで、その日は余計に忘れられない一日としてミスラの心に刻まれたのだった。
