- Ships within 7 daysShips by Anshin-BOOTH-PackPhysical (direct)500 JPY
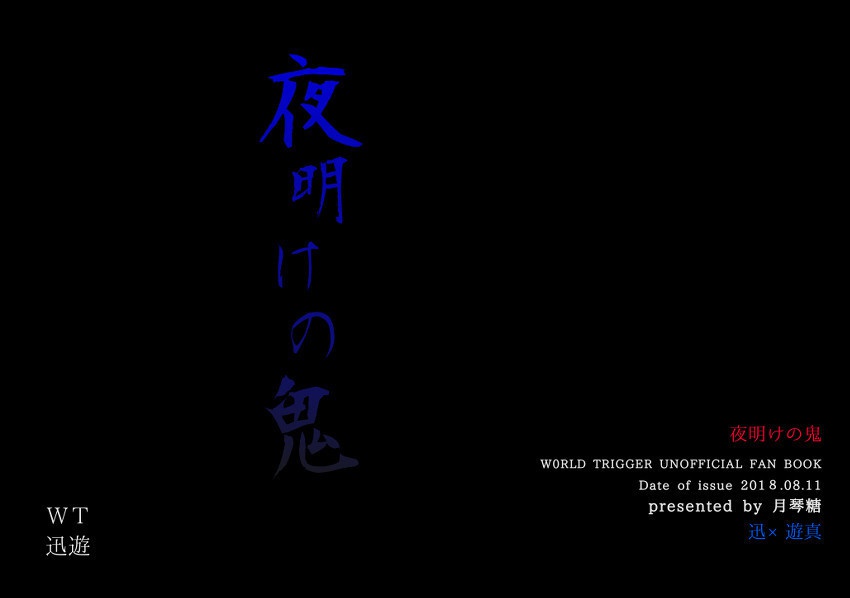
コミックマーケット94で発行した迅遊で時代物パロ小説です。人を襲う”鬼”や”魔物”を退治する者達に加わった空閑遊真は、自分を救ってくれた迅悠一が、鬼ではないかと疑われていることを知る…。というお話です。
夜明けの鬼 - サンプル -
子どものころに、鬼を見た。 大雨であたりが煙る中、鬼は蒼い妖気をまとって、その立ち姿はゆらりと揺らいで見えた。 空は一面黒雲に覆われている。ときどき雨脚が鈍ったかと思うと、また勢いを盛り返す。 大粒の雨が落ちるたびに水飛沫があがる。そこらの家の屋根にも塀の上も、地べたでも。絶え間なく滴り落ちて、足元で早瀬のように音を立てて雨水が流れる。 通りでは何人もが倒れ、もう動かなくなって雨に打たれていた。 やがて泥にまみれる人びとを、じっと見下ろすように鬼はうつむいていた。 土砂降りをものともせず、身体の周りが金色にうっすらと光るばかりで、髪の毛も着物も、襟から覗いた肌も濡れていない。 そんな姿を、迅は、なぜかしら淋しそうだと感じた。 あんなにも脆く、儚いように佇む姿を、迅は他に知らない。 以来、どこかで淋しそうにしている人を見れば、まるで(あのときの鬼みたいだ)と、思ったりするのだ。 ……だけれども。 あのときの鬼ほど、やはり孤独を感じさせる存在は、いやしない。 何者も寄せつけず、誰に触れられるのも拒んでいる、そういう感じがしたのだ。 鬼とは、そういうものなのだろう、と、子ども心に、迅は刻み込んだ。 あれから、何度も、その光景を思いだす。 真っ黒な空の下、叩きつけるような土砂降りのもと、地面に幾人もが倒れて、鬼がそれを見下ろしている。 思いだすたびに、迅は、果たして本当に自分の見たことなのか、ただ、見たという記憶があるだけなのかが、わからなくなってきた。 本当に、自分は鬼を見たんだろうか。 そんなことを、考えるようになった。 爽やかな風が吹いて、裾や袖をはためかせる。 物干竿の前に立った烏丸京介が、空を仰いで目を細めるのが見えた。 つられて遊真も見上げる。すっきりと晴れて、端の方にだけ、さっと刷毛で描いたような白い雲がほんの一筋流れていた。 昨日までの大雨が嘘のような天気だ。これなら洗濯物もよく乾くだろう。 「遊真、それでぜんぶか?」 洗い終わった着物や手拭いなどで山盛りの桶を抱えてきた遊真に、京介が言った。 「ぜんぶだよ、これで」 「よし、じゃあ干しちまうか」 袖まくりをすると、一番上に積まれたものから物干竿へかけていく。 「おれも手伝う」 遊真は、次に干すものを取って広げて、彼に渡す役を引き受けた。 風が、ざあっと吹くごとに晴れた空はますます澄んでいくような気がする。 二人は黙ってきびきびと働いていたが、そのうちに、遊真はなんとなく手を止めて陽光の眩しさを見やった。屋根瓦に陽の光がきらりと反射した。 「どうかしたか」 京介が帯をかけ終えたところで問いかける。 「ううん。……林藤さんは、まだ寝てるのかなって」 首を振りながらも、洗濯物を片づける手は止めずに、ふと考えていたことを口にした。 もう朝という時間ではないし、林藤は日頃から寝坊をするわけでもない。どちらかといえば早起きの性分だろう。なのに今日はまだ起きてこない。それは、ほとんど夜通しで忙しく働いていたせいである。 屋敷に戻って一息つけたのは、明け方に近かったのではないか。他にも、京介や、遊真も、昨晩は行動を共にしていたのだが、ここの主人である林藤匠は事のお終いの後始末まで済ませてから帰宅したので、そんなに遅くなったのだった。 夜半のまだ雨が強い中、林藤が遊真に向かって声をかけてきた。 ーーあとは大人に任せて、おまえは先に帰れ。 びしゃびしゃと雨に打たれて、林藤の隣で、そうだ、というように木崎レイジがうなずいていた。 遊真は不服を訴えたが、ここはいいから代わりに屋敷の守りを頼むと言われて帰りを急かされ、しばらくすると京介も帰ってきた。 心配ないから、今晩はもう休もうと話しているところに、レイジが戻った。 小止みになった雨を聞きながら遊真は眠りに落ち、うつらうつらして、林藤が帰宅したらしい物音をぼんやりと聞いた。 「さっき、俺が出てくるときは、まだだったな」 洗濯物で湿った手を乾かすように、京介はひらひらと片手を振る。 「あれぐらいの事はたまにある。そう珍しくもない」 京介は無表情というか無愛想な顔つきだ。機嫌が悪いとか怒っているのではなく、彼は大方いつもこんな感じだった。 「誰も怪我してないし、被害は少ないほうだぞ」 「……うん」 「なんだ。何に引っかかってるんだ」 洗濯物が山と積まれた桶だったが、そろそろ底が見えてきていた。 青空の下、鍛錬場の方から勇ましいかけ声が聞こえてくる他は静かなものだ。 昨日も、確かこんなふうだった。夕方までは平和で、みんなのんびりしていた。 ーー魔物が人を襲っている。どうやら、鬼も近くにいるらしい。 見張り番から、そんな伝令が届くまでは。 鬼と聞いて、屋敷中が騒然となり、一刻も早く駆けつけねばと我先に外へ飛び出していく。 遊真もそのうちの一人だったが、隣に追いついてきた林藤が、何か呟いて走るのを止めた。 どうしたのかと様子をうかがうと、なにやらぎょっとした顔で遠くを睨んでいる。 「こりゃあ、くるな」 何がだろうとさらに訝ると、ふいに雷鳴が轟いた。 一天、にわかにかき曇り、暗雲が垂れ込める。 暴風が吹き始め、雨粒をぶつけてきた。あまりの天気の変わりように、遊真は唖然としてしまった。 「急ぐぞ」 遊真の肩をぽんと叩き、林藤は厳しい表情だった。そのときの彼は空が荒れることを予期したように思えた。 「もともと、魔物や、特に鬼なんかは、天気が崩れたり日没のころを狙って出やすいんだ」 京介は、特に不思議がるふうでもない。 「だから林藤さんも、鬼が出るなら雨がくるだろうって思ったんだ。それだけだよ」 「……そうかなぁ」 遊真は首を傾げてため息を吐き、それから身を屈めて桶の底の洗濯物を拾い上げた。 今日は風も穏やかだ。腕を上げ下げするたびに、着物の袖を、ただ優しくそよがせる。 洗濯物を受け取る、京介の目が問いかけていた。何がそんなに気がかりなんだ、と。 問われても、遊真は、はっきりと答えられない。 鬼が出るから、雨がくる。魔物祓いを担う者にとってなんら珍しがることではない。 鬼が出るから、雨がくる。 それがわかりきったことなら、あの普段から飄々として滅多に動じない林藤が、ああも、ぎくりとした顔をするなんてどうにも解せない。 彼が察して、「くるな」と言ったのは、本当に雨のことだったのか。 「ここが終わったら、俺はレイジさんを手伝いにいく」 京介は言い、物干にかけた手拭いを左右から引っ張り小気味好い音を響かせる。 「遊真、おまえは」 「ねえ昨日の夜なんだけどさ」 話しかけられたのと、遊真がつい早口で言いだしたのが、ほぼ同時だった。 「迅さんって、あの場にいたよね?」 京介は目を丸くし、当惑したようにまばたきした。 「迅さん? そりゃ、いたけど……。話もしたし」 遊真は真似をしたように目をしばたかせる。 ふいに、やや強めの風が吹き、物干にずらりと並んだ洗濯物がいっせいにひるがえった。 二人がいる庭の奥から、小さな細い道を辿った先が、この屋敷の居候である、迅悠一の使う離れだ。 昨日の夜の魔物退治の最中、遊真の記憶では、どこを探しても迅悠一の姿は見つからなかった。 いたというのは本当なのか、思いだそうとすればするほど、不安が募るのだった。 空閑遊真が、ここの屋敷に来たのは二ヶ月ばかり前のことだ。 そのおよそ半月前に、父親を亡くしていた。旅の途中で鬼ーーというか、怪異に襲われたのである。 父の空閑有吾は相当の手練れで、その父を返り討ちにするのだから、怖ろしく強い鬼だったのだろう。 一人になった遊真は、途方に暮れていたわけでもないが、まだ子どもの身でさてこれからどうしようかと考えあぐねていたところへ、父の昔の知り合いだと名乗る、林藤匠という男が訪ねてきた。 「おまえの親父さんに、俺はたいそう世話になってね。いろんな事をそりゃあ山ほど教わったんだよ」 羽織袴を着込んで、黒縁の眼鏡をかけている。くだけた口調だが、物腰も服装もきちんとしていて、それなりの身分であることをうかがわせた。 林藤は遊真に、自分のところへ来るように言った。 「おまえも親父さんから鍛えられて、魔物とはやり合えるんだろう。だったら、うちの連中といっしょに闘ってもらいたいんだ」 遊真は、林藤の申し出を受け入れ、屋敷で面倒をみてもらうことにした。 村の、遊真を預かっていた役人には話をつけて、林藤が主人を務める屋敷へと向かう。朝出て、歩いて夕暮れまでかかるという。 道中で、林藤は遊真に、これまでどんな暮らしをしていたのかを聞いたり、自分が守りを任されている地所の様子を聞かせたりした。 やがて陽も沈みかけ、もう屋敷も見えるぞ、と言われたころに、遊真はずっと気になっていたことを尋ねた。 「ねえ、おれが、あの村にいるのが、よくわかったね」 遊真は、父親が亡くなったことを誰かへ伝えたりはしていない。 自分の知らないうちに、いつの間にか、何かそういう手筈になっていたのかと思ったのだ。 「んー、まぁ、なあ」 それについて林藤は、ほとんどまともに答えない。 「おれと親父はずっと旅をしていたし、あの村にいたのは偶然だったんだけど」 「……そうだなぁ。勘っていうか、運が良かったな」 本心でないのがすぐにわかる。不思議がる遊真の質問を、のらりくらりと交わし、着いたらまず誰それに会わせねえと、などと言っていたが、 「ーーおい」 突然、声音が低くなる。隣を歩く遊真に向けたものではなかった。前方に人がいる。 「おかえりなさい、林藤さん」 そう言ったのはまだ若そうな男だ。遊真は林藤の後ろからこっそりと姿を見ようとした。 「その子が、そうか。ちゃんと会えたんだ」 「あぁ、おまえの言ったとおりにな」 顔を覗かせた遊真を、彼も覗き込もうとしていた。 背が高く、どちらかといえば細身の青年だ。薄茶色の髪の毛に、青い瞳。白絣の着流しに雪駄履きで、懐手をして気楽そうな笑みを浮かべている。 「林藤さんが、間に合って良かった」 なんのことだろう、と遊真は首を傾げた。 現れた男の、きれいな青い瞳には目を奪われた。それにしても、初対面のはずなのに、まるで、ここで会えるのを待ちわびていたような風情で、遊真をじっと見つめてくる。だが、見つめてくるくせに、目を合わせるとか声をかけてきそうなそぶりはない。 「おまえ、もう夜になる。あんまりふらつくなよ」 「わかってるよ」 ゆらりとこちらに背を向け、それじゃあ、というように片手を上げた。 「……言ってもするんだろうけどな」 遊真は、迷ったものの、林藤の羽織の裾を掴んだ。 「さっきのは、誰?」 「ーーうちの居候だよ」 「イソウロウ?」 「悪い意味じゃない。あいつも闘えるし、強い奴でな」 遊真が見上げる角度から、林藤の顔には影が覆い被さり、何を思っているのかわかりづらい。 「あいつは、迅悠一だ。いずれ、おまえと引き合わせるつもりではいた」 そう言って林藤は指で首筋をかいた。 ふと遊真は、とっぷり陽が暮れている景色を見渡す。 暗くなるのがどうも早い。父親に教わった今の季節に陽が沈むはずの時刻からすると妙な感じがした。 なんだか、急ぎ足に夜が迫ってくる。否、昼が終わろうとしている。まるで追い立てられるように。 何にだ。そんなことができるのは、怪異の類ぐらいなのではないか。 背筋に、ゾッと悪寒が走った。 得体の知れないものが、今までそこにいたように。 「さて、と。あとちょっとだからな」 林藤の口調がわざとらしいほど明るく聞こえ、戸惑う遊真を急かして歩き始める。 道端の藪で虫がさえずりだしたが、湿った風が吹いてくるとぴたりと止んだ。 長い坂の上に屋敷はあった。薄闇の中、玄関先にともされた提灯の明かりが、ほっとするような暖かい色合いに見えたことを、後々まで遊真は覚えていた。 桶を洗い場に戻してから、遊真は離れに行ってみた。 母屋では、どこも手入れが行き届いているけど、離れは小道の脇に雑草が生い茂っている。 湿った地面に、草履の底がぺたぺた鳴った。離れの裏は竹林で、葉の擦れる音が絶えず聞こえる。 「迅さん」 表ではなく、庭にまわって声をかけた。 返事はなかった。遊真は縁側から様子をうかがう。 まだ昼前だというのに、離れの中はなんだか暗い。 庭も同様で、裏に生える背の高い竹のせいか、ここは常に暗いのだ。 (母屋の方に行ったのかな) 特に用事があったでもなし、しばらく佇んでみるが、静寂とひやりとした空気を味わっただけで、やはり戻ろうとしたそのとき。 「遊真」 背を向けた後ろから声がした。 庭は、隔てる戸もなくそのまま竹林と続いているが、まるでたった今、そこから抜け出してきたように、迅が立っている。 「なんだ、来てくれたばかりなのに、もう帰るのか」 「……迅さん、どこにいたの」 「どこって、あちらだよ」 振り向きもせず、迅は肩越しに竹林を指した。 「あんなところで、何してたの」 「ちょっとね、昨晩の後始末を」 そんなことを言うが、灰色の縞の着物姿で手には何も持っていない。整った顔に愛想の良い笑みを浮かべて、こちらへ近づいてくる。 「後始末って、どんなの」 「そいつは生憎、教えられないなあ」 と言って、肩をひょいとすくめてみせた。 竹林とは逆の、屋敷の表玄関の方から話し声が聞こえる。どうやら訪問客でもあったようだ。 「おれも、あとで母屋に行くよ」 目配せして、なにも怪しまれる事なんてしてないよ、とでもいわんばかりである。 「じゃあ、おれも、そのときにいっしょに戻る」 遊真が言うと、「そうか」とだけ答え、口を薄く開けて微笑んだ。 まるで、ため息を吐いたように思えた。
