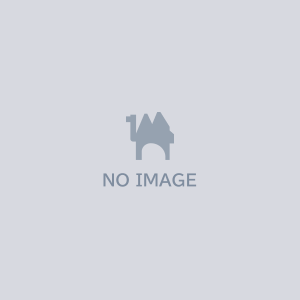sound note 室井康雄 3章 アニメ私塾 ビジネスモデル構築編
- ダウンロード商品¥ 1,500

アニメ私塾の室井康雄さんオーディオブック「SOUND NOTE」。 1章 少年時代編 52分 2章 アニメーター編 1時間7分 3章 アニメ私塾 ビジネスモデル構築編 41分 4章 サロン運営編 38分 SOUND NOTE アニメ私塾 室井康雄 オーディオブック 第3章 アニメ私塾 ビジネスモデル構築編 41分 レビュー 文=山井淳生 第3章 アニメ私塾 ビジネスモデル構築編 「上手くなると楽しくなるんですよ」 9年3ヶ月のアニメーター人生を経て、アニメ私塾を立ち上げた室井。この章では、アニメ私塾とはなんぞやという導入から、ビジネスモデル構築の試行錯誤、約300人もの塾生を抱えるようになった今、そしてこの先の展望について語られる。 「絵が上手くなってほしい」室井の言葉はごくごくシンプルだ。ものすごく簡単に言うならば、アニメ私塾とは、絵が上手くなるためのオンライン上の私塾であり、学校や会社といった環境、さらにはアニメという垣根すら超えて、室井がこれまで培ってきた技術が提供される場である。 前述の室井の言葉は、「上手くなると楽しくなるんですよ」と続く。これは、教育者としての室井の、真髄にあたる言葉ではないだろうか。下手なりに楽しいという領域を越えたところに、上手くならないと楽しくない領域がある。その楽しさをもっと知ってもらいたいという、室井の理念が見て取れよう。 料金体系や、カリキュラムなどについても詳しく言及されるが、そこは本編を確認してもらいたい。筆者が注目したいのは、途中で話題にあがる、絵を描く上で、才能の有無ではない領域を知るという話だ。 絵が描ける、描けない、ということに関して、才能の有無の問題ではなく、普遍的な傾向として、やりがちなミスがあるという。 例えば、髪の毛のボリュームを小さく描きがち、という弱点は、かなりのひとが陥りがちな傾向にあるという。アニメ私塾で学び、100人規模の他者の絵に触れることによって、ひとりで描いていても、数人で描いていても気づけない傾向に気づく。これは、共通の課題に大勢の塾生が取り組むがゆえの、アニメ私塾のメリットだろう。才能の有無の関与しない領域で、何をどう改善すればよいのかという、絵が上手くなるためのプロセスを学ぶことで、再現性高く、階段を登っていけるのだ。 室井は「絵を描くのはカラオケに似ている」とも語り、絵が上手いひとが偉いという「画力カースト」についても批判的な立場を取っている。 前者は、歌うことと同じように、絵を描くことも「楽しい」という率直な気持ちで取り組んでほしいという例えであり、技術の向上だけを目的にすると、絵の上手い上位数名以外、幸せになれなくなってしまうことになる。それは違うのではないかという立場が後者である。 つまり、絵が上手くなることは目指すべき点であるが、その出来不出来や才能の有無が、そのひとを計る物差しになるわけではなく、あくまで「楽しむ」ことに主眼を置いているのだ。前述したように、ある一線を超えたあとは「上手くなる」=「楽しい」という領域に入るため、すこしややこしいが、その目的意識を見誤ってはならないのである。 他方、絵が上手くなることがすべてではないとは言いつつも、室井自身が、絵が上手くなること自体への信仰を持ち続けている、という話も興味深い。添削は、塾生だけでなく教育者も絵を描くから、両者の技術が向上する場でもあるのだ。室井は今、教育者であり、アニメーターも引退した。しかしながら、未だに「絵描き」ではあり続けているのである。教える⇔教わるの関係性を超えたところで、「絵描き」としての、室井と塾生の切磋琢磨がある。そのことが、アニメ私塾がこれだけのコンテンツに成長した秘訣のひとつではないだろうか。 もちろん、アニメ私塾の強みはそれだけではなく、室井の徹底したマーケティングやマネタイズの理論がある。アニメ私塾のビジネスモデル構築に際して、その詳細を、これでもかと言わんばかりに語られるのがこの章でもある。インタビュー中の中武の弁にもあるが、自分の技術をもって独立したいと考えているようなクリエイターにとって、必聴の章であること間違いない。 それに加えて、アニメ私塾の強みとして特筆したいのは、塾生同士のコミュニティの場を設けたことだ。これは続く最終章「サロン運営編」にてより詳しく扱われる。そちらも合わせてお楽しみいただきたい。