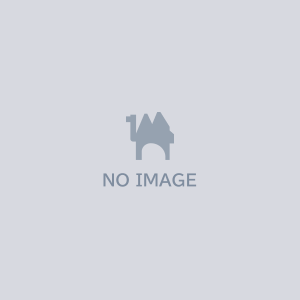sound note 室井康雄 4章 サロン運営編
- ダウンロード商品¥ 1,500

アニメ私塾の室井康雄さんオーディオブック「SOUND NOTE」。 1章 少年時代編 52分 2章 アニメーター編 1時間7分 3章 アニメ私塾 ビジネスモデル構築編 41分 4章 サロン運営編 38分 SOUND NOTE アニメ私塾 室井康雄 オーディオブック 第4章 サロン運営編 38分 レビュー 文=山井淳生 第4章 サロン運営編 「どんな要素があると、もっとアニメが個人の時代になると思いますか」 ついに最終章、サロン運営編に突入する。はじめに断っておきたいのは、この章で扱われる話題は、サロン運営に留まらないという点だ。タイトル通り、アニメ私塾のオンラインサロン「ネット村」に関する話題がメインに据えられてはいるものの、インタビューの後半では、アニメ私塾やアニメ業界全般に関する、室井と中武の熱いトークが繰り広げられる。アニメ私塾やオンラインサロンに興味があるひとはもちろんのこと、そうでないひとにも、ぜひ聴いてもらいたい章である。 まず「ネット村」についてだが、アニメ私塾のコミュニティ機能のみを独立させたもので、塾生でないひとも、年会費さえ払えば参加できる。つまるところ、アニメ私塾に興味がある人、絵が上手くなりたい人の交流を目的とした場であるが、サロン内では、アニメに限らない多岐にわたる話題が飛び交い、さながらヤフー知恵袋のような状態にあるという。その様子について中武が「集団のための個人ではなく、個人のための集団」と言い表すのが印象的だ。相互の経験値の共有がなされる場が今オンライン上にあるというのは、驚くべきことだろう。 そして、サロン運営の話題から派生する形で、アニメ制作に関心を持つお客さんを増やすために、制作の様子を発信するというアイデアや、もし室井が制作進行だったら……といった注目のトークが次々に繰り広げられる。いずれもぜひ本編で確認してほしい。 インタビューも後半に差し掛かると、アニメ私塾の塾生にして、WIT STUDIOに所属するアニメーター・田中正晃から預かってきた三つの質問が投げかけられる。質問はそれぞれ、アニメ私塾の未来、アニメの未来、そして室井に未来に関するもので、どれも聞きごたえ抜群だが、なかでも「どんな要素があると、もっとアニメが個人の時代になると思いますか」という言葉が印象的だ。商業アニメ以外に、自主制作アニメも精力的に制作する田中ならではの質問だろう。新海誠の登場以降、自主制作や、少人数によるアニメ制作が多くのひとの関心の的であることは間違いないが、いつだってアニメ制作のメインストリームは大人数だった。それが「個人の時代」になることを田中は見据えている。その視座もまた、見逃せないものだ。 この問いに対して室井は、個人で作れる尺の問題をあげつつ、「個人の時代にはなるけど、アニメを作れるひとはそんなにいない」と語り、「アニメを作れるスキルは強い武器になる」とつなぐ。これは、ツールの進化やネット上のノウハウの増加が、アニメ制作へのハードルを下げている一方で、アニメを作れるひとが急激に増したわけではないという、アニメ私塾を率いる室井の経験に戻づく発言だ。学生時代に自主制作アニメを作っていた室井と、現在進行形で制作中の田中。「個人制作」という切り口においても、先輩後輩の関係にあるふたりの質疑応答は、そのさらに後輩にあたるような読者にとっても、大変参考になるものだろう。 ここで紹介したのは質疑のトークのうちのごくごく一部だが、田中の熱量マシマシの鋭い問いを、室井が全力で打ち返すという構図は一貫している。この熱いやりとりを、ぜひとも実際に聴いてみてほしい。 このあと、「アリとキリギリス」や「裸の王様」といった逸話に例えて、室井の理想の絵描き像や、今求められている人物像が語られ、インタビューは終わる。キリギリスのような、目の前の楽しいを、アリのように積み重ねてほしい、という室井の思いは、長きに渡ったトークの〆に相応しいものだろう。インタビュー後の室井と中武の、充実感のあるやり取りがオーディオブックに含まれているのもポイントだ。阿佐ヶ谷ロフトでのトークの終わりのような、満足感と、イベントが終わってしまった一抹の寂しさを覚えてしまうような、きれいな終わり方だった。 これにて「SOUND NOTE アニメ私塾 室井康雄 オーディオブック」のレビューは終了する。アニメ私塾やWIT STUDIOとも縁遠く、プロのライターでもない自分が、どんなスタンスで書けばいいのかと思い悩み続けた全4章でもあったが、トークを繰り返し繰り返し再生しながら、室井や中武の思想に触れた経験は、アニメ業界就職前、そして卒論執筆中の自分にとって、得難い経験であったことは間違いない。何よりこれらのテキストが読者にとって、オーディオブックに興味を持つきっかけとなるものであるようにと願う。 敬称略の文もここまでだ。レビュー執筆のチャンスをくださった中武さん、それを承諾してくださった室井さん、そして読んでくださった皆様、ありがとうございました!