【半夕】群青空はラプソディ
- Ships within 7 daysShips by Anshin-BOOTH-PackPhysical (direct)1,050 JPY
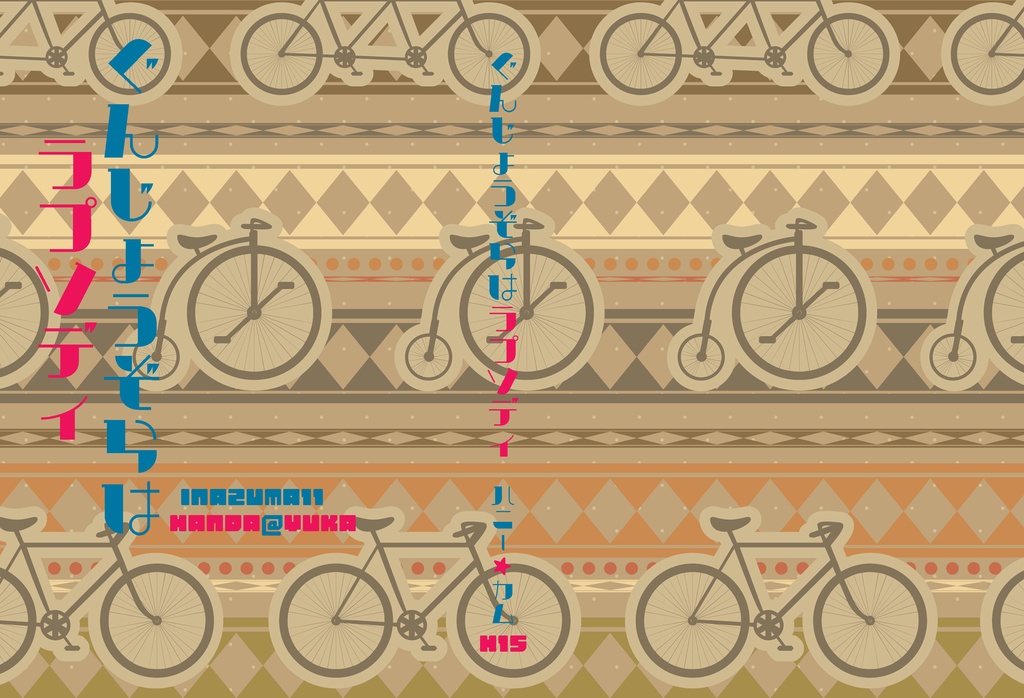
■B6/300P ■半田と夕香ちゃん。短編39話。 ■閉鎖済サイトの半夕テキストを加筆・修正したものです。書き下ろしありです。 ■7年後未来型設定のため、半田は21歳、夕香ちゃんは14歳からスタートです。
群青空はラプソディ
身頃も見頃で、花束を。 開いたそれは、芯のそれ。 帯は明るく、おびただしい。 いいんだ、明日が平和なら。 「半田のお兄ちゃんに、お願いがあるの!」 ばっと俺の目の前に立ちはだかる右手に、目盛りのついた細長いものを握っている。左手には家庭科の教科書を抱える。中学校三年度、と表紙にあった。きらきらとしたダークブラウンの光彩が大きく俺を見上げる。はっきり言って嫌な予感しかしなかった。 右手の指に引っかかっているメジャーをぎゅっと握る彼女は、これっぽっちも悲壮じゃあない。むしろ、楽しくて仕方がない、といった様子だ。俺がめくっていた頃とはイラストが違うんだな、と彼女の手にある家庭科の教科書をにらんだ。 半田真一がにらんでいたとしても、教科書には罪はなかった。世界にも日本にも稲妻町にも罪なんてない。当然ながら罰だってない。俺が懸念しているのは、雷門中学校三年度の家庭科の実習内容が、昔と変化していないのじゃあないか、という一点だった。 雷門中学校三年度の家庭科には、なかなかに難解な実習内容があった。当時十五歳だった半田真一は、白米を炊いて味噌汁とおかずを二品程作った方が有意義じゃあないのか、と首を傾げたものだ。 学校側の見解としては、白米と味噌汁とおかずは文化祭の屋台に化けていた。お好み焼きや焼きそばやたこ焼きに変化したそれは、はたして等号で結んでしまっていいものか、と俺の心に波紋を投げかけた。まあ、文化祭の屋台に文句はなかったけれど。 問題なのは屋台ではない。前置きするまでもなく、お好み焼きでも焼きそばでもたこ焼きでもない。注意しなくてはならないのは、炭水化物ばかりが並べられる屋台への参加条件だ。加えて、文化祭で授業がつぶれるからといって、油断してはならない。中学校の授業内容には規定があるから、さばけなかった分はあとでしわ寄せがくる。たいてい、そういうのは前よりも後で責任を取らされると決まっていた。自然の摂理だ。 ああ、ええと、そうじゃあなくて。 文化祭の屋台には参加条件があった。屋台の運営は三年度の総合と家庭科の時間割が当てられていた。総合はクラスでの協力・学習で、家庭科の実習で制作した浴衣を着用するのが義務づけられていたんだ。要するに、浴衣が完成していないと参加ができない。大変だったな、と数年前を思う。提出できずに家庭科の成績がどうにかなっても構いやしなかったけれど、文化祭の屋台には出たかった。学校側の思惑としては、大層な成功を納めたわけだ。まったくもって悔しいことに。 問題は、俺の目の前で嬉しそうにメジャーを握り家庭科の教科書を抱えている彼女だった。この時期にその出で立ちでいるということは、と冷や汗をかく。六月末の稲妻町はまだ梅雨まっただ中だ。毎日じんわりと湿度の高い空気が俺を圧迫する。彼女はそんな気候には無縁で、いつでもからりと晴れ渡った空みたいだったけれど。 稲妻町前駅前図書館(名前がややこしい)の一番広いフロア。受付カウンターから少しだけ離れた位置には、十人がけのテーブルが設置されている。ライトブラウンのテーブルに隣り合わせで腰かけた俺に、彼女は意を決したように宣言する。「家庭科の授業で浴衣を作るの。半田のお兄ちゃんのサイズを測らせてくれないかな」 死刑宣告かな、と感じた。それから、弾劾裁判かな、とも思う。半田真一がもしやなんらかの過ちを犯してしまったとしても、最後まで俺の無実を信じてくれそうなのが豪炎寺夕香だった。だのに、なんたることだろう。俺はなにか罰を受けなくてはならないようなことを、つい最近やらかしたりしただろうか。ああ、神様、と信じてはいないそれに祈った。 どうして俺のなんだろう、とまぶたを伏せながら、「提出物としてアウトじゃないのかな」と今度は雷門中学校の家庭科教師に祈る。もう、俺を担当してくれた先生は別の学校に移動になっている気がするから、知らない先生かもしれなかったけれど。彼女はぱあっと嬉しそうにするので、ぎくりと嫌な予感が増えて世界に広がっていく。 「今年からね、自分の浴衣を持っている人は、家族の浴衣でもよくなったの!」と満面の笑みだ。半田真一はいつの間に豪炎寺夕香の家族になったんだろう。数年後に、そうなれたらちょっといいかもしれない、と考えたことが皆無ではなかった。でも、そんなの夢物語なはずなんだけどな、と唸る。 「お父さんのだって言って提出するから、大丈夫!」 なにが大丈夫なんだろう。すみません、豪炎寺先生。娘さんが俺のせいで不正を。家庭科の先生もすみません。俺の後輩が先輩のせいで不正を。だなんて、半田真一は考えたりはしない。やれやれ、と大きく息を吐き出した。 なにか理由があるんだろうな、と思う。彼女は本来、積極的にルールを破ったりはしないタイプだ。だからきっと、なんらかの目的があるんだろう。まあ、その目的が重要なのであれば、彼女にとってルールはないのと同様でもあるので、それを破らないギリギリのラインで目的をはたそうとするだろう。ああ、どちらも俺の知っている彼女だ。はあ、ともう一度息を吐く。ねえ、夕香ちゃん。だから教えてよ、と半田真一は君にその目的を問わずにはいられないんだよ。 ◇ 「どうして俺のなの?」 「わたしはもう浴衣を持っていて、半田のお兄ちゃんは浴衣を持っていないから」 「家族のは可でも、俺は家族じゃないよ?」 「だから、父のです、って申請するから」 「必要でない嘘はつかない方がいいと思うよ。あと、豪炎寺先生が泣くと思う」 「わたしは泣かないと思う。じゃあ、婚約者のです、はどう?」 「俺たちそんなのしてないよね」 「わたしはしてもいいのだけれど」 「ありがとう。でも、そうじゃないよね」 話がさっぱりと進まないな、と体が傾きそうになる。七月頭の稲妻町は梅雨まっただ中だったけれど、図書館にはガラスの窓越しにピカピカとした日差しがまぶしい。梅雨明けはまだなのに、なんだか止められないようなまばゆさだった。 どうにもこうにも不可思議で、「俺が浴衣を買えば万事解決なのかな」と訊ねてみる。即座に、「それはダメ!」と返された。ああ、まだなにか隠している、と俺は上半身がますます傾くようだったんだ。はあ、と溜息と一緒に頬杖をつく。背の高い天井の上部は細長い窓ガラスが並んでいて、キラキラと光った。梅雨の合間のなんだろうな、と納得する。 「浴衣の生地がね、紺なの」 俺がうんざりとした顔をしたからなのか、彼女はようやくぽつぽつと話し出した。「麻がかなり入っている生地でね、さらさらしているの。手触りがいいの。浴衣って結構暑いけれど、涼しく着られそうな感じなの」と言葉を綴る。「紺にね、白で柄が入っていて、太かったり細かったりするストライプなの。だから、半田のお兄ちゃんでも嫌じゃあないかなあ、って」と音を続ける。「そうだね、朝顔や向日葵は遠慮するよ」とは言葉にはしなかった。彼女はじっと俺を見据える。 「わたしがこの間買ってもらった浴衣がね、やっぱり紺に白で柄が抜かれているの。金魚柄なの。だから、半田のお兄ちゃんが紺でストライプのを着てくれたら」 彼女は堂々とした握り拳にでもなってしまいそうだ。「ちょっとお揃いみたいだな、と思って」の台詞だけ少し照れくさいのか声が小さくなる。いきなり照れられても、と俺は困惑する。なぜって、照れている彼女は可愛いからだ。どきり、とわずかに心臓も跳ねた。 「わたし、半田のお兄ちゃんとお揃いなのって自転車だけだから。ああ、ホリゾンタルとスタッガードでフレームが違うけれど。でも、あの二台はタイプ違いだからそっくりだし」 そういうのを夢見てたなんて知らなかったな、と意外だ。まじまじと彼女を見返したら、「ああ、違うの。そうじゃないの」と弁解だって降る。 「わたしもはっきりしたお揃いはあんまりかっこよくないなあ、と思っていて。でも自転車はカラーも違うし、浴衣はなんとなくお揃いに見えなくもない、っていうくらいが恥ずかしくなくてちょうどいいなあ、って……」 豪炎寺夕香はかなりのところで口の達者な女の子だ。だから、こんなにしどろもどろなのはとてつもなく珍しかった。「支離滅裂かなあ」と泣き笑いさえしそうになる。なにを迷っているんだろう、と俺の心の中では摩訶不思議が席巻する。 「ええと、夕香ちゃんは家庭科の実習で浴衣を作らなくちゃあならない」 「うん」 「浴衣が完成していないと、文化祭の屋台に参加できない。俺が中三の時はそうだったんだけど、ルール変わってる?」 「変わってない」 「制作する浴衣は、自分のものでなくとも構わなくて、家族のものでも可に変更された」 「そう」 「で、合ってる?」 「うん」 ふむ、と胸の手前で腕を組んで思案する。すると、やっぱりクリアしていない条件は「家族のもの」というところだけなんだ、と頷いた。話を続けながら、「夕香ちゃんのクラスの家庭科の先生の名前は?」と訊ねてみれば、なんと俺の既知の先生だった。移動してなかったんだ。まあ、私立だしな、と納得する。これははたしてラッキーかアンラッキーか。うーん、と一つ唸ってから決心した。 「七年前に卒業した、元雷門サッカー部の半田真一の浴衣を作ります。彼とは、未来的に家族になる可能性がゼロではありません」 「え?」 「って話して、家庭科の先生に許可を取って。あの先生面白いことが好きだったから、運がよければオッケーしてくれる。断られたら、夕香ちゃんは自分の浴衣を作るんだ」 彼女はぱちり、と不思議そうにまばたきをした。「俺、不器用だから中三の時に浴衣を作るの大変だったんだ。先生にたくさん迷惑かけた。すごく遅れて提出したし、こんなに縫えない子も珍しい! とか笑われた。だから、たぶん俺のことを覚えてると思う」と説明する。 覚えてなくていいんだけど。覚えていてほしいことは叶えられず、忘れてほしいことも叶えられない人生だ。なんでだか、そうと決まってるんだ。ああ、ちょっとでいいから、半田真一の人生にも栄光あれ! 問題は、半田真一の浴衣が完成したとしても、それが豪炎寺夕香と揃いに見えるということよりも、現雷門中学校三年生みんなとお揃いということじゃなかろうか。彼女はそんな俺の気持ちには気づかずに、今にも吹き出しそうにしている。楽しそうだ。あのさ、今なにか面白いことあった? 彼女はメジャーを握りしめる。「分かった。明日、先生に許可をもらってくるね」の台詞の途中でとうとうくすくすと笑った。なんだか心外だ。俺にとってルールをギリギリ守れる妥協点なんだけれど。 じゃあ、ちょっとだけサイズを測らせてね、と彼女は気が早い。 シュッ、とメジャーを広げては、俺の右肩と左肩に当てる。 しばらく無言なので、どうしたのかな、と振り返れば。 半田のお兄ちゃんって結構肩幅広いね、と恥ずかしそうに呟かれた。 (いや、俺普通だから、一般体型だから! と気恥ずかしくなって叫んだ)
