desire
- 支払いから発送までの日数:7日以内在庫なしあんしんBOOTHパックで配送予定物販商品(自宅から発送)¥ 800
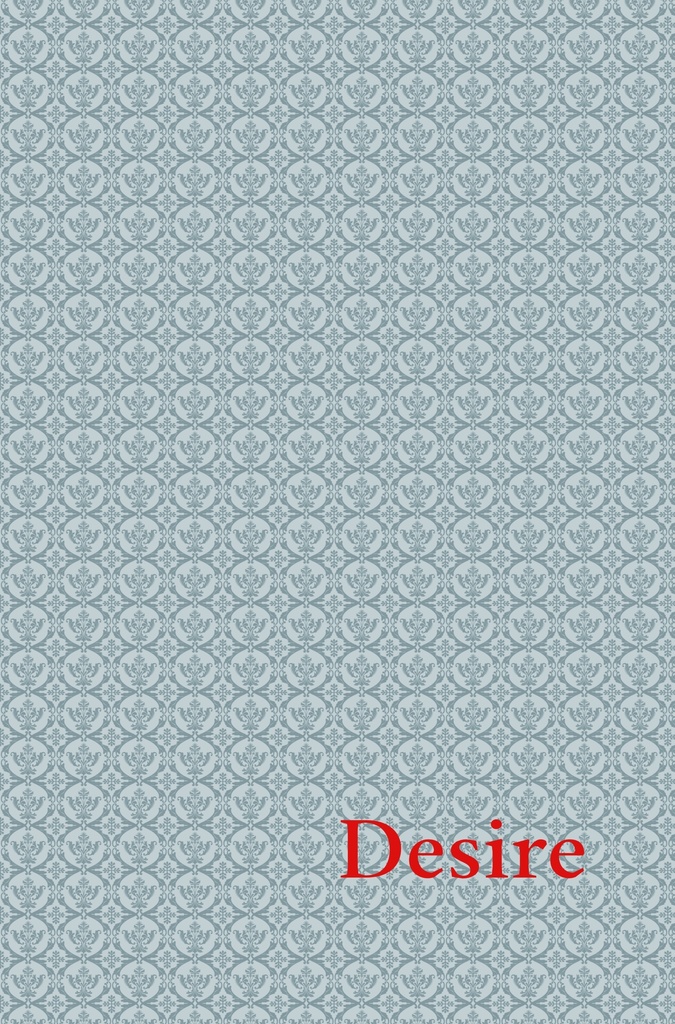
5月3日【超夢中物語2019】にて発行の新刊です。 desire ちづみか/文庫/120p ◯巳影に恋人ないし好きな相手が出来た、と千鶴が勘違いする付き合ってるちづみかの話 ◯恋を知らない千鶴と、どうしようもなく恋をしてる巳影 ◯だいぶ病んでます(千鶴が) ★付き合ってます ◯いちゃいちゃベタベタします(年齢制限のある描写はありません) ◎ハッピーエンドです あんしんBOOTHパック(ネコポス)での発送となります。
desire本文サンプル
最初にその存在に気が付いたのは先週の頭だった。ここ数日で、まだニットやセーターはしまえないが、冬物のコートは早朝か夜遅くにしか要らないくらい暖かくなってきた。日本の気候的に寒の戻りを計算しても、コートはもう春物で支障ないだろう。それでも念の為に主人の分は冬のコートを一着だけ残して、クロゼットの整理を簡単に終えた日だ。よく覚えている。あの日も今日のように、雲ひとつない晴天が冴え冴えとしていた。 三年生が授業の関係で外に出ている今日、千鶴は半日の休日を貰った。休日といえどやるべきことは山ほどあるし、他に特に予定もなく、仁の部屋でタブレットを操作している。主人の帰りは夕方遅くになると言っていたから、それまでに会議資料の整理と夕飯の有無を確認しなければ、と頭の内でスケジュールを組み立てながら画面をタップしたところで、ふと気配を感じて顔を上げた。 千鶴、といつものようにノックと同時にドアを開ける姿を振り返りざまに睨めば、ざっくりと首元がV字に開いたケーブルニットの袖を肘の下まで捲った巳影が、手にしたスマートフォンをひらひらと振っている。 「ノックしろって何回言えば判るの」 「したじゃん」 「同時に開けたら意味ないんだけど」 「なあに、急に開けられて困ることでもしてたの?ちづちゃんのえっち」 「マナーの話をしてるの。まあ低俗な巳影に言っても理解できないか」 ニヤニヤと笑う安い挑発には乗らず、大きく肩を竦めて手元へ視線を戻す。これ見よがしにため息をつけば、けらけらと軽やかな笑い声が近付いた。 「久々に言われた、テイゾク」 「言われ慣れてるでしょう」 「不名誉〜」 にっこり笑ってやれば、眉を下げたニヤケ面が首を傾げる。ひらり、ともう一度スマートフォンを揺らした巳影が、ソファの縁へ軽く腰をおろした。 「で、本題ね」 「ああ、何かあったの」 「いつもちゃんと用事あるでしょ?」 「どうでもいいことばっかりね」 「それは否定しないけど」 くすり、と笑う顔は見ずに、小さく肩を竦める。 「千鶴に会いたいってだけじゃ用事にならない?」 「はあ?」 視界の端で首を傾げた巳影に、きつく眉根を寄せる。くすくすと笑う目元は少し苦かった気がしたけれど、千鶴は気のせいだと決めつけて、胡乱に睨んでおいた。軽薄な口調で揶揄われるのはもう慣れている。 「で、なに」 「はいはい、生徒会から伝言ですよ」 ひらひらと片手の平を翻す巳影は、反対の手に持ったスマートフォンを手早く操作して、何件かの会議要綱を読み上げる。そのまま主人に伝える為にタブレットの画面を切り替えて、千鶴は巳影から視線を逸らした。スマートフォンを持つ左手の中指に存在感強く輝くシルバーを、千鶴は出来れば認識していたくない。 巳影に恋人が出来たらしいと気付いたのは、あの指輪のせいだった。 巳影が欲しい、と思ったのは、もうはるか昔のことのような気がする。認めたくはないが、千鶴がきちんと認識するより前から、巳影のことを特別には思っていたのだろう。我ながら曖昧な感情は今まで経験したことのないもので、理解しきれないまでも、千鶴の人生には不必要なものだった。今だって不必要だと思うけれど 、それでも自覚してしまったのだから仕方がない。 何度も捨てようと、忘れようとした思いはそうすればするほど千鶴を蝕んだ。捨てられないのなら諦めて開き直るしかないし、開き直るとなれば千鶴は全てを自分の思い通りにする。これまで生きてきて強く欲しいと思ったものはそうないけれど、欲しいと思ったならば手に入れるべきだ、と諦めたのだ。 結果、巳影のことは手に入れたと思う。少なくとも千鶴はそう思っている。巳影の時間を潰して、巳影の体も手にした。それだけで欲求は満たされる筈だった。 別の人間へ何かしらの感情を向けること、例えば巳影が欲しいという願望を持つこと、それは千鶴にとっては主人への裏切りでもある。千鶴の、気持ち、と呼べるものは全て、仁への忠誠しかない。千鶴を仁の傍へ置いておけるように教育したのは槙の家だけれど、それでも例えば槙の家が仁にとって邪魔になるのであれば、情も未練もなくすぐに捨てられるだろう。そもそも情や未練など、生きていく上で邪魔でしかないものだと千鶴は教わってきた。だからそうしたところで褒められこそすれ、憎まれることもない。 (中略) 「以上です。何かご質問は?」 顔を上げた時雨に答える前に、千鶴は主人の後ろ姿を確認した。資料から目を上げず、仁は軽く頷く。 「こちらからは特にありません」 改めて時雨へ視線を戻して千鶴が答えれば、極めて事務的に微笑んだ時雨が視線だけで反対側へも伺いを立てる。仁の向かいには一生が資料を手に座っていて、その隣の席はまだ空席だった。 「俺からも大丈夫だ」 「わかりました。それでは順に始めていきたいと思います」 議題一覧のプリントを端に追いやり、手早く資料の束を出した時雨を観察するように眺める千鶴は、つい数分前の時雨の言葉を反芻している。会議には全員が揃うことを必ず守らせようとする男ではないが、それでも理由の無い欠席には口煩いのが時雨だ。その時雨が、時間になっても現れなかった巳影にはひと言も触れず、仁と千鶴が入室したところで会議を始めてしまった。特に時間を気にしたり急いだりしている風でもない時雨に、浅霧はどうした、と当然の疑問を口にしたのは仁だったけれど、小さく肩を竦めた一生に代わり、彼はいいんです、と首を振った時雨は特に何の説明もなく会議要綱を読み上げ始めた。今日が会議の日だということは巳影も忘れてはいないはずだ。昼休みに気怠そうな巳影と会議の話をしたのはまだ記憶に新しい。遅刻してくる日は千鶴にメッセージを送って上手いこと言っといて、と投げてくるのが常であったけれど、今日はその連絡も無い。そういえば最後の授業が終わるのと同時に教室から姿を消した巳影の不在の理由を、この場で唯一知っているらしい時雨は涼しげな顔で滞りなく議長の役割を遂行している。 何故貴方が知っているんですか、と聞きたくて堪らなかった。しかしそれは、何故自分は知らないのだ、と駄々をこねるようなものだ。主人の手前無様な真似は出来ず、千鶴は表情を消して紅茶の準備を始める。 (中略) 週末、連れてこられたのは予想通りにいつもの渋谷の店だ。ダーツで勝負をして、スロットを打つ巳影の後ろから茶々を入れ、ビリヤード台へ移る。巳影が矢を放つ隙に、スロットマシンに瞬間的に集中する間に、キューを磨く合間に、千鶴は抜け目なく目を配る。 巳影の『恋人』はなにも学園内にいるとは限らない。男なのか、女なのかも判らないけれど、とにかく千鶴は全ての人間を疑った。最近では千鶴にも気安い挨拶をするバーテンダーの男、明らかにわざとらしい偶然を装って毎回出会う常連の女、ドリンクを取りに行く巳影にすかさず声をかける顔見知りの男。疑えば全てが怪しかったけれど、それでもその全ては違うと千鶴の勘が告げる。巳影の態度が変わらないのだ。もっとも、それも装っているだけかもしれないけれど。 「ちづちゃん考え事ー?随分余裕じゃん」 「だって勝ってるし」 「うっわ、絶対負けないからね」 「はいはい、せいぜい頑張って」 狙いを定める巳影に笑う。ここへ来ると、ふたりはいつも勝負をしていた。最初の時のように何かを賭けることはあまり無かったけれど──たまには賭けゲームになるのは、巳影がいるのだから仕方がないことではある──他愛もなく勝敗で盛り上がるのは楽しかった。今日はダーツで千鶴が僅差で勝っている。スロットでツキを取り戻したらしい巳影も健闘はしているけれど、今日は千鶴の調子の方が良いらしい。だいたいがナインボールでの勝負になるビリヤードもこのまま行けば勝てそうだけれど、巳影は負けている局面からの逆転劇ほど真価を発揮するから、もちろん油断はしていない。 「って言っても、今日調子悪いんじゃない巳影」 「そーいうこと言っても動揺しないからね」 白々と肩を竦めた巳影は、それでも一度体を起こした。僅かに場所を変えて、再びキューを構える。ダーツのラインに立つ時の、スロットの目を読む時の、キューを構える時の巳影の顔を見るのは割合に気に入っている。ふざけた笑みは消え去り、綺麗な横顔が真剣に黙り込む。これが千鶴とチームを組んで他の客との対戦になるとまた別なのだが、巳影は千鶴と一対一で立つ時は、いつも真剣にゲームを運んでいく。嘘くさいまでの真っ向勝負が最初の頃は胡散臭かったけれど、今となってはそういうゲームをしているのだろう、と納得はしている。それはそれで、千鶴もやりやすくて良い。 たまに見かける、例えば孝臣とチェスをしている時や、千里のゲームに付き合っている時ともまた違う横顔は、これこそ本当に千鶴だけのものだ。たくさんの誰かに向ける巳影の顔は千鶴には向かないけれど、この勝負にムキになる真剣な顔は、千鶴以外には向けられない。だからいつも、その凛とした綺麗な横顔を、思わずじっと見てしまう。 (後略)
